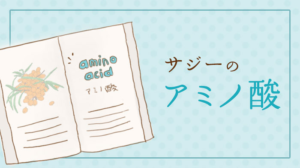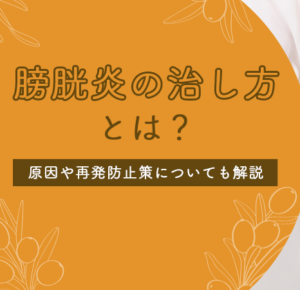
サジーコラム
Column
コラーゲンって結局何?効果と摂り方を解説【食べても意味ないは誤解】
栄養 美容 2025.01.24

コラーゲンは、美容や健康に関心のある方にとって、なじみのある成分かもしれません。肌のハリを保ったり、関節の柔軟性をサポートしたりする働きがあり、サプリメントや食品などで取り入れている方も少なくありません。
一方で「食べても意味がない」という声もありますが、これは誤解です。摂取方法に留意すれば体内でしっかりとその役目を果たしてくれます。
本記事では、コラーゲンとは何かを説明するとともに、効果や摂取方法についてわかりやすく解説します。
コラーゲンとはタンパク質の一種

コラーゲンとは、体内に多く存在するタンパク質の30%を占める主要成分で、人体の構造や機能を支えるうえで欠かせない存在です。アミノ酸が多数結合した繊維状になっており、皮膚、骨、軟骨、血管、腱など、体のあらゆる組織に分布しています。
とくに、皮膚では真皮の大部分を構成し、ハリや弾力を保つ役割から美容成分としても広く知られています。また、関節のクッション剤となる軟骨や内臓を包む膜もコラーゲンが多く含まれる組織です。
コラーゲンは年齢とともに減少・変性しやすく、それが肌のたるみや関節の不調につながるケースも少なくありません。美容だけでなく、健康維持の観点からも大切な成分といえるでしょう。
コラーゲンの構造
コラーゲンは、3本のひも状のタンパク質がねじれながら絡み合った三重のらせん構造でできています。この構造により、高い強度と柔軟性を兼ね備え、体内の結合組織をしっかりと支える役割を果たしています。
ポリペプチド鎖は、主にグリシン・プロリン・ヒドロキシプロリンといったアミノ酸から構成されており、これらの規則的な配列が構造の安定性を保つ要因です。また、コラーゲンの分子は繊維状に集まり、皮膚や腱、骨、軟骨などの強靭な支持組織を形成します。
コラーゲンは29種類もある!
コラーゲンは実に29種類も存在し、それぞれ異なる部位や役割を担っています。以下では、代表的な5種類の特徴を解説します。
Ⅰ型コラーゲン
Ⅰ型コラーゲンは、体内でもっとも多く存在するタイプで、皮膚・骨・腱・歯・靭帯などの強度が求められる組織に広く分布しています。
繊維状の構造をもち、引っ張りに強いという特徴があり、肌のハリや骨の硬さを支える主成分です。とくに、真皮層に多く含まれ、美容の観点でも重要視されています。
Ⅱ型コラーゲン
Ⅱ型コラーゲンは、主に関節の軟骨や眼の硝子体に含まれ、弾力性や滑らかな動きを保つ役割を果たすタイプです。軟骨の主成分であり関節をスムーズに動かすクッションのような働きもあるため、加齢や疾患によって減少すると、痛みやこわばりの原因になる可能性があります。
Ⅲ型コラーゲン
Ⅲ型コラーゲンは、Ⅰ型とともに皮膚や血管壁、内臓などに存在し、柔軟性や再生力を支える働きをもっています。とくに若い肌に多く含まれ、肌のしなやかさや弾力の維持に関与するため「若さを保つコラーゲン」とも呼ばれるタイプです。
加齢とともに減少しやすく、肌の老化や血管の硬化に関係することが知られています。
Ⅳ型コラーゲン
Ⅳ型コラーゲンは、ほかの型と異なり繊維を形成せず、網目状の構造をもっている点が特徴です。基底膜と呼ばれる、細胞と組織をつなぐ薄い膜の構造に多く含まれており、腎臓や肺、血管、皮膚の基底部に分布しています。
この膜がしっかりと機能することで、細胞の安定や物質の透過性が保たれています。
Ⅴ型コラーゲン
Ⅴ型コラーゲンは、Ⅰ型やⅢ型とともに存在し、それらのコラーゲン繊維の形成や安定化を助ける補助的な役割を担うタイプです。とくに、胎盤や肺、角膜などの組織に多く含まれており、細胞の発達や成長にも関与します。
量は多くありませんが、組織の構築をサポートする存在として活躍します。
コラーゲンの主な働き
コラーゲンは、皮膚や骨、関節、筋肉など全身の組織に関与する成分です。その働きは、多岐にわたり、日々私たちの体を支えています。
ここでは、コラーゲンが果たす多彩な役割のなかでも、代表的な5つの働きに注目し、具体的な機能を解説します。
1:肌に潤いやハリを与える
コラーゲンは、肌の真皮層に多く存在し、繊維状に張り巡らされる構造によって皮膚を内側から支えています。そのため、肌のハリや弾力を保ち、みずみずしい質感を維持するうえで欠かせません。
加齢や紫外線の影響でコラーゲンが減少・劣化すると、肌はたるみや乾燥、小ジワといった変化を起こしやすくなります。美しい肌を保持するには、コラーゲンの質と量の維持が大切です。
2:骨の強度を高める
コラーゲンは骨のなかにも豊富に存在し、骨の「しなやかさ」を保つうえで重要な役割を果たしています。コラーゲンが繊維状を構築し、その周囲にカルシウムを含むミネラルが沈着して強くて折れにくい骨が形成される仕組みです。
そのため、不足すると骨の柔軟性が失われてしまい、衝撃に弱くなるリスクが高まります。健康な骨を維持するには、ミネラルだけでなくコラーゲンの十分な供給も不可欠です。
3:関節の動きをスムーズにする
関節の滑らかな動きを支えている成分が、軟骨に多く含まれるⅡ型コラーゲンです。関節を覆う軟骨組織の構造を維持し、骨同士が直接ぶつかるのを防ぐクッションのような役割を果たしており、関節の健康を保つうえで欠かせません。
加齢や負荷の蓄積によって減少・劣化すると、軟骨が摩耗し、関節の動きがぎこちなくなったり、痛みを引き起こしたりするリスクが高まります。
4:筋組織や腱を丈夫にする
コラーゲンは、筋肉と骨をつなぐ腱や靭帯、さらに筋膜などの結合組織にも多く含まれており、それらの強度や柔軟性の維持に不可欠です。とくに、運動や日常動作で体を支える部位においてコラーゲンは組織の損傷を防ぎ、耐久性を高める働きをします。
加齢や過度な負荷によって劣化した場合、腱や靭帯が弱くなり、ケガのリスクが高まる可能性があります。
5:血管のしなやかさを保つ
血管の壁を構成するうえでも、コラーゲンは重要な役割を果たしています。弾力性がありしなやかな血管が形成されることで、血流の圧力に耐えながらも柔軟に拡張・収縮を支える仕組みです。
不足したり劣化したりすると、血管の弾力が失われて硬くなり、高血圧や動脈硬化のリスクが高まります。
加齢で体内のコラーゲンは減少する丨不足による主な不調
コラーゲンは年齢とともに自然に減少していく成分です。20代後半からも減り始めるケースもあり、減少とともに関節や血管、筋肉などの機能低下につながります。
ここでは、コラーゲン不足によって起こりやすい主な不調について解説します。
肌のたるみやシワ
コラーゲンは肌の真皮層でハリや弾力を保つ働きをしており、美しい肌を支える基盤ともいえる存在です。加齢によりコラーゲンが減少・劣化すると、肌の支えが弱まり、たるみやシワといった見た目の変化が目立ちやすくなります。若々しい印象を保つには、コラーゲンの維持が不可欠です。
髪の毛が細くなる・抜け毛
髪を支える頭皮や毛根まわりの組織にもコラーゲンが関与しており、その働きによって髪の成長環境が保たれています。頭皮の弾力や血流の低下、毛根への栄養が届きにくくなる現象は、加齢が引き起こすコラーゲン不足による不調のひとつです。
結果的に、髪の毛が細くなったり抜け毛が増えたりする要因になります。
関節の痛み
関節を覆う軟骨にはⅡ型コラーゲンが豊富に含まれており、関節のクッションとなり、滑らかな動きを支えています。加齢や負荷の蓄積によりコラーゲンが減少・劣化すると、軟骨がすり減り、関節に痛みや違和感が生じやすくなります。
骨粗鬆症
骨はカルシウムだけでなく、コラーゲンによってもしなやかさと強度が保たれています。そのため、コラーゲン不足は骨粗鬆症を引き起こす要因のひとつです。
加齢でコラーゲンの減少した場合、骨の弾力が失われ骨密度も下がりやすくなります。
動脈硬化や高血圧
血管の壁もコラーゲンで構成されており、しなやかさを保つうえで欠かせない存在です。加齢や生活習慣の影響でコラーゲンが減少すると、血管の弾力が失われ、動脈硬化や高血圧のリスクが高まる原因となります。
コラーゲンを多く含む食品
コラーゲンは体内で生成される成分ですが、年齢とともにその量は減少します。そのため、日常の食事から補うことが大切です。
コラーゲンを多く含む代表的な食品は、鶏の皮や手羽先、豚足、牛すじ、魚の皮や骨などが挙げられます。とくに、煮込み料理やスープに使われる食材は、加熱によってコラーゲンが溶け出し、効率的に摂取できる点が特徴です。
また、フカヒレやうなぎ、なまこなどの高級食材にもコラーゲンは豊富に含まれています。ただし、これらの食材はカロリーが高い傾向にあるため注意が必要です。
コラーゲンを取り入れる際は、ほかの栄養素とのバランスも意識しましょう。適切な摂取により、体内のコラーゲン量を保ちやすくなり、肌や関節などのコンディションを整えるのにも役立ちます。
コラーゲンを効率よく摂取する方法
コラーゲンは食品から摂取可能ですが、ただ取り入れるだけでは効率よく体内で活用されにくい可能性があります。ここでは、コラーゲンを無駄なく活かし、吸収効率を上げるための摂取方法を解説します。
ビタミンCと鉄分が豊富な食材と一緒に摂る
コラーゲンを摂取する際は、ビタミンCや鉄分と組み合わせると、体内での合成や吸収がよりスムーズになります。
とくに、ビタミンCはコラーゲン生成に欠かせない栄養素です。赤ピーマンやブロッコリー、いちご、キウイなど摂取しやすい食材に含まれているため、普段から意識して取り入れましょう。
また、鉄分はコラーゲンの構造形成に関与しており、レバーや赤みの肉、ほうれん草などが豊富な供給源です。これらの栄養素を一緒に摂ることで、効率よくコラーゲンを体内に取り入れやすくなります。
最初からコラーゲンペプチドの形で摂取する
コラーゲンはそのままの状態では分子が大きく、すべてがそのまま吸収されるわけではありません。摂取されたコラーゲンの一部は、体内で分解されてペプチドの形となり、小腸から吸収されます。
そこで注目されている成分が、コラーゲンを加水分解によって小さく加工した「コラーゲンペプチド」です。
コラーゲンペプチドは、通常のコラーゲンに比べて吸収性が高く、効率的に体内に取り入れられます。ドリンクや粉末、サプリメントなどさまざまな形で市販されており、日々の食事で不足しやすい栄養を補う手段としても役立ちます。
継続的に摂取する
コラーゲンは一度に多く摂取すれば効果が高まるというものではなく、日々の生活のなかで継続的に取り入れることが大切です。体内での合成や維持には時間がかかるため、一定量を継続して摂取するほうが、肌や関節、血管などの健康によい影響を与えるとされています。
サプリメントやドリンク、食事など、ライフスタイルに合った方法で無理なく摂取し、コラーゲンの働きをより効果的に引き出しましょう。
適度な運動をする
コラーゲンの摂取効果を高めるには、食事だけでなく適度な運動も欠かせません。運動によって筋肉細胞から分泌される「マイオカイン」という物質が、皮膚細胞の活性を促し、コラーゲンの生成にもよい影響を与えるとされています。
合成をサポートする環境を整えるためにも、ウォーキングやストレッチなど、日常に取り入れやすい運動を習慣にすると効果的です。食事と運動の相乗効果により、内側からの美容と健康維持が期待できます。
コラーゲンの経口摂取は意味がないって本当?
「コラーゲンは食べても意味がない」といった声を耳にすることがあります。こうした認識は、コラーゲンが一度アミノ酸に分解される性質から広まった誤解に過ぎません。
近年の研究では、摂取後に「コラーゲンペプチド」として吸収され、体内のコラーゲン生成を助け、効果を発揮する働きが確認されています。ここでは、経口摂取後のコラーゲンについて解説します。
コラーゲンペプチドとは
そもそもコラーゲンは、多数のアミノ酸が連なってできた高分子のタンパク質です。その分子量は30万と大きく、そのままでは体内に吸収されにくい性質があります。
コラーゲンペプチドは、コラーゲンを加水分解して分子量を小さくした成分です。低分子の状態のため吸収効率が高く、体内で再度コラーゲンの生成をサポートする働きがあります。
たとえば、肌の保湿力を高めたり、真皮層のコラーゲン量を増やせたりする点も、コラーゲンペプチドの注目される効果のひとつです。
アミノ酸に分解されたコラーゲンもムダにはならない
摂取されたコラーゲンは体内で一度アミノ酸にまで分解されるため「食べても意味がない」といわれるケースが多く見られました。しかし、アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚などのあらゆる組織の材料となり、体を維持するために必要なタンパク質を合成するために使用されます。
つまり、アミノ酸に分解されたコラーゲンも決してムダにはなりません。「コラーゲンを食べても意味がない」という説は、摂取後のアミノ酸の働きを見落とした誤解といえるでしょう。コラーゲンの効果をより高めるためにも、正しい摂取方法を選択することが大切です。
コラーゲンを摂取するタイミングと量
コラーゲンを効果的に取り入れるには、摂取するタイミングや量にも留意する必要があります。ここでは、コラーゲンをいつ、どの程度摂取すればよいのかを解説します。
いつ摂取するのがいい?
コラーゲンは、摂取するタイミングによって体内での働き方に差が出ると考えられています。とくに、就寝前や空腹時は吸収効率が高まるとされる時間帯です。
また、成長ホルモンが分泌されやすい夜間は、肌や骨の修復が活発に行われるため、コラーゲンのサポート効果をより引き出せる可能性があります。
1日の摂取量はどのくらい?
コラーゲンの摂取量に明確な基準はありませんが、一般的には1日5〜10g程度が目安とされています。これは、肌や関節などの健康を維持するうえで適切な量です。
食品だけでは補えない場合、サプリメントやドリンクなどをうまく活用するとよいでしょう。
過剰摂取するとどうなる?
コラーゲンは、大量に摂取したからといって効果が高まるものではありません。一日の目安となる摂取量を超えれば過剰摂取になります。
大きな副作用はないものの、人によってはお腹の張りや下痢などの消化器系の不調を感じることがあります。タンパク質としての摂取量が極端に多くなると、腎臓に負担をかける可能性も否定できません。
また、皮脂が過剰に分泌されやすくなるため、ニキビや肌荒れなどにも注意が必要です。
まとめ
コラーゲンは、私たちの体を維持するうえで欠かせないタンパク質です。不足すると、関節の不調や抜け毛、高血圧などのリスクが高まるため、日頃から意識して摂取する必要があります。
ただし、過剰に摂取すると胃腸や皮膚などに不調をきたしかねません。効率的かつ安全にコラーゲンを取り入れるには、一日の摂取量や取り入れるタイミングに注意することが大切です。年齢や体調に応じて適切に摂取し続けながら、健康維持を目指しましょう。