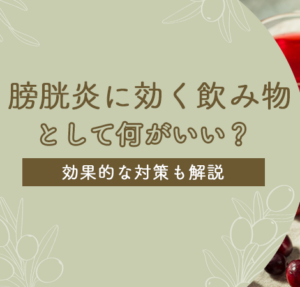サジーコラム
Column
頻尿の原因と自宅でできる対策を解説!今日から始める生活改善のポイント
栄養 健康 2025.08.08

トイレの回数が多く、仕事に集中できない、夜中に何度も目が覚めてしまう、そんな頻尿の悩みを抱えていませんか。頻尿は日常生活の質を大きく下げる症状です。しかし、原因を理解して適切に対策をとれば、改善できる可能性があります。
この記事では、頻尿の具体的な症状から原因、そして自宅で今日から始められる対策方法までを、泌尿器科学会のガイドラインに基づいて分かりやすく解説します。
薬に頼る前に生活習慣を見直したい方や、重大な病気のサインではないか確かめておきたい方は、ぜひ最後までお読みください。

頻尿とは具体的にどういう症状?
頻尿とは、トイレが近い、または排尿回数が多いと感じる症状のことです。日本泌尿器科学会では、朝起きてから就寝までの排尿回数が8回以上を目安としています。ただし個人差があるため、8回未満でも「多くて困る」と感じるなら頻尿といえます。
通常、膀胱には200~300ミリリットルほどの尿をためられ、1日5~7回の排尿が一般的です。頻尿の方は膀胱に十分ためられず、少量でも尿意を感じてしまいます。
頻尿は加齢とともに増え、40代以降では多くの人が経験します。女性は尿道が短く、出産や加齢で骨盤底筋がゆるみやすいため、男性より悩みやすい傾向があります。
まずは1日の排尿回数や尿量、水分摂取量を記録し、自分の排尿リズムを客観的に把握することが改善の第一歩です。
夜間頻尿とは?
夜間頻尿とは、就寝中に排尿のため1回以上起きる状態をいいます。医学的には1回以上ですが、臨床では2回以上起きる場合を治療の対象とすることが多いです。
夜間に何度も起きると睡眠が分断され、日中の疲労や集中力の低下を招きます。とくに高齢者は、暗い中での転倒リスクが高まり注意が必要です。実際、夜間頻尿のある人は、ない人に比べて転倒による骨折の危険が約2倍になるといわれています。
主な原因は3つあります。
● 夜間に尿が多く作られる「夜間多尿」
加齢による抗利尿ホルモンの低下や、日中のむくみが夜に戻ることが関係します。
● 膀胱に尿をためにくい「膀胱蓄尿障害」
過活動膀胱や前立腺肥大症などが代表的です。
● 「睡眠障害」
眠りが浅く、中途覚醒のたびに尿意を感じやすくなります。
夜間に排尿量が多ければ夜間多尿、少なければ膀胱や睡眠の問題が疑われます。まずは排尿日誌を付けて、自分のタイプを確認してみましょう。
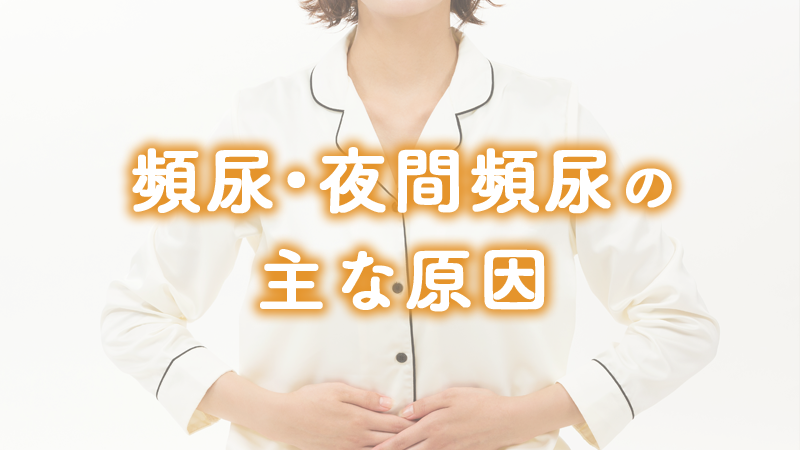
頻尿・夜間頻尿の主な原因
頻尿の原因はさまざまで、病気によるものだけでなく、生活習慣や心身の状態が関係していることもあります。ここでは、主な原因を「疾病」と「生活習慣・心身の状態」の2つに分けて見ていきましょう。
原因となる疾病
頻尿の背景には、膀胱や腎臓、ホルモンの異常など、さまざまな病気が隠れていることがあります。ここでは、頻尿を引き起こす代表的な疾患と、その特徴を簡単に見ていきましょう。
過活動膀胱
過活動膀胱とは、膀胱に尿が十分たまっていないのに、勝手に収縮してしまう病気です。急に強い尿意を感じて我慢できなくなる「尿意切迫感」が特徴で、40歳以上の約8人に1人が悩んでいるといわれます。
主な原因は加齢ですが、脳卒中やパーキンソン病など、脳や脊髄の異常によって起こることもあります。症状が進むと、トイレに間に合わず尿が漏れてしまう「切迫性尿失禁」をともなう場合もあります。
心因性の頻尿
身体に異常がないのに、トイレのことが気になって何度も行ってしまう状態です。ストレスや不安などの心理的要因が関係しており、尿量は正常でも強い尿意を感じます。眠っている間は排尿を気にしないため、夜間頻尿はほとんど見られません。
膀胱炎
主に細菌感染によって膀胱に炎症が起こる病気で、女性に多く見られます。頻尿のほか、排尿時の痛みや残尿感、尿の濁り、血尿などが現れます。膀胱の神経が刺激されるため、少しの尿でも強い尿意を感じます。
前立腺肥大症
男性特有の疾患で、加齢により前立腺が大きくなり尿道を圧迫することで起こります。尿の勢いが弱く、排尿に時間がかかるのが特徴です。膀胱に尿が残りやすく、残尿感や頻尿をともないます。
糖尿病
インスリンの働きが不足し高血糖状態が続くことで、喉の渇きとともに多飲多尿になります。進行すると末梢神経が障害されて膀胱機能が低下し、頻尿につながります。
子宮筋腫
子宮にできる良性腫瘍で、筋腫が大きくなると膀胱を圧迫し、頻尿を引き起こします。月経量の増加や下腹部の圧迫感をともなうことがあります。
骨盤臓器脱
出産や加齢で骨盤底筋がゆるみ、膀胱や子宮が下がる状態です。臓器が膀胱を圧迫することで頻尿や尿漏れが起こります。
睡眠障害
眠りが浅く途中で何度も目が覚めると、そのたびに尿意を感じやすくなります。実際には尿量が少ない場合が多く、睡眠の質を整えることで改善します。
原因となる生活や心身の状態
頻尿は病気だけでなく、日常の習慣や心身の状態によっても起こります。ここでは、生活の中で注意したい主な原因を紹介します。
水分の摂りすぎ
「1日2リットルの水を飲むとよい」と言われますが、飲みすぎると尿量が増え頻尿の原因になります。目安は体重1kgあたり1日20〜25ml、体重60kgなら約1,200〜1,500mlが適量です。
緊張・不安
膀胱は精神的影響を受けやすい臓器です。緊張や不安を感じると、実際には尿がたまっていなくても尿意を感じることがあります。
体温の低下
体が冷えると膀胱の血流が悪化し、尿をためる働きが低下します。冬場や冷房の効いた環境ではとくに注意が必要です。
加齢にともなう機能低下
抗利尿ホルモンの分泌が低下すると、夜間の尿量が増えます。また膀胱の弾力性や骨盤底筋の機能も低下し、頻尿を引き起こします。
原因特定のために泌尿器科の受診がおすすめ
頻尿の裏には、膀胱がんや前立腺がん、糖尿病などの重大な病気が隠れていることがあります。自己判断せず、早めに専門医へ相談しましょう。
血尿、排尿時の痛み、急な体重減少、強い喉の渇き、尿の勢いが弱いなどの症状がある場合は、早急な受診が必要です。泌尿器科では、問診や尿検査、超音波検査などで原因を特定します。病気が見つかれば治療を行い、見つからない場合も過活動膀胱などの診断を受けて適切な治療が可能です。
セルフケアはあくまで補助的な方法です。まずは受診し、原因を知ることから始めましょう。

【男性も女性も】自宅で改善!日常生活でできる頻尿対策
ここからは、性別を問わず日常生活で実践できる具体的な頻尿対策を紹介します。これらの対策は、泌尿器科学会のガイドラインで推奨されているものや、複数の医療機関で効果が認められているものを中心に厳選しました。
すべての対策を一度に始める必要はありません。できることから少しずつ取り入れて、継続することが大切です。
【はじめに】排尿日誌を付けよう
頻尿対策の第一歩は、排尿日誌で自分の状態を知ることです。排尿の時刻や尿量、飲水量などを数日間記録すると、原因を客観的に把握できます。
1回の排尿量が200〜300ミリリットルなら正常範囲、100ミリリットル以下なら膀胱に尿を溜めにくい可能性があります。夜間の尿量が全体の3分の1を超える場合は夜間多尿が疑われます。
適切な水分量を意識する
頻尿だからといって水分を極端に控えると、脱水や膀胱炎を招くおそれがあります。大切なのは「飲まないこと」ではなく「ちょうどよく飲むこと」です。
1日の水分摂取量の目安は、体重1kgあたり20〜25ミリリットル、体重60kgなら、1,200〜1,500ミリリットルが目安です。このなかには食事で摂る水分も含まれるため、飲み物としては1日500〜1,000ミリリットルほどが適量です。
尿の色をチェックするのもよい目安になります。薄い黄色なら適量、透明に近い場合は飲みすぎ、濃い黄色なら水分不足のサインです。とくに朝や入浴後など、汗をかいたタイミングで少しずつ水分を補うようにしましょう。
夜間頻尿を防ぐには、就寝2~3時間前までにコップ1杯程度を分けて飲むのがおすすめです。一度に大量に飲むと夜間の尿量が増えるため、日中のうちにしっかり水分を摂っておくことも大切です。
また、塩分の摂りすぎは体内に水分をため込み、結果的に尿量を増やします。夕食時の味付けを少し薄くするだけでも効果的です。
アルコール・カフェインを避ける
アルコールとカフェインには、利尿作用と膀胱刺激作用の両方があります。利尿作用により尿量が増え、膀胱刺激作用により膀胱が過敏になるため、頻尿が起こりやすくなります。
カフェインは、コーヒー、緑茶、紅茶、ウーロン茶、エナジードリンクなどに多く含まれています。完全に避けることは難しいかもしれませんが、1日の摂取量を減らすよう心がけましょう。コーヒーなら1日1〜2杯程度に抑えるのが目安です。
カフェインの含まれていない麦茶やルイボスティー、ハーブティーなどに置き換えるのもよい方法です。とくに就寝前の摂取は夜間頻尿の原因となるため、夕方以降は控えることをおすすめします。
アルコールについても同様に、とくに就寝前の飲酒は避けましょう。アルコールは利尿作用が強いだけでなく、睡眠の質を低下させることで夜間頻尿を悪化させます。適量を超えると頻尿や残尿感を引き起こすため、お酒を控えることで症状が改善される方も多いです。
辛いものを食べない
辛いものを食べると、膀胱の粘膜が刺激されて頻尿につながることがあります。これは唐辛子に含まれるカプサイシンという成分が原因です。
2006年の研究によると、週に5回以上辛いものを食べる方は頻尿になりやすいという結果が報告されています。普段から頻繁に辛いものを食べている方は、週に数回程度に減らしてみるとよいでしょう。
外出先ではトイレの位置を確認する
外出先でトイレの場所が分からないことへの不安感が、心理的に尿意を催すことがあります。事前にトイレの位置を確認しておくことで不安が軽減され、頻尿対策として効果的です。
スマートフォンの地図アプリで近くのトイレを探したり、施設に入った時点でトイレの位置を確認したりする習慣をつけるとよいでしょう。
痩せる
肥満は頻尿の原因となることがあります。BMIが27以上の方は、それ以下の方に比べて頻尿リスクが1.5〜2倍になるといわれています。肥満になると骨盤が広がり、骨盤底筋がうまく働かなくなります。
また、内臓脂肪が膀胱を圧迫して尿意を感じやすくなります。適正体重を維持することで、こうした膀胱への負担を減らすことができます。
膀胱訓練を行う
膀胱訓練とは、尿意を感じたときにすぐトイレに行かず、少し我慢することで膀胱の容量を増やす方法です。泌尿器科学会のガイドラインでも推奨されているエビデンスのある治療法です。
具体的な方法は次の通りです。
①尿意を感じても、まずは5〜10分程度我慢してみる。
②慣れてきたら徐々に時間を延ばし、最終的には15〜30分程度我慢する。
これを繰り返すことで、膀胱は「この人はもう少し尿を溜めてから排尿するんだ」と認識し、尿意を感じるタイミングが遅くなります。結果として、尿を溜められる容量が少しずつ増えていきます。目標は、1回の排尿量が200〜400ミリリットル、排尿間隔が3〜5時間となることです。
ただし、とくに女性の場合は長時間我慢しすぎると膀胱炎のリスクが高まるため、無理のない範囲で行いましょう。また、尿路感染症や前立腺肥大症などの疾患がある場合は、医師に相談してから始めてください。
骨盤底筋を鍛える
骨盤底筋は、膀胱や子宮、直腸などを支える重要な筋肉です。衰えると、尿漏れや頻尿の原因になります。
基本動作は「肛門を締める」ことです。排尿を途中で止めるときに使う筋肉を意識して引き締めましょう。
①仰向けに寝た姿勢で:膝を立て、膣や肛門の筋肉に力を入れて5〜10秒キープ。1セット10回を1日3セット。
②座った姿勢で:背筋を伸ばし、骨盤を立てた状態で肛門を締める。
③椅子に座った姿勢で:足を肩幅に開き、背筋を伸ばして行う。仕事中にも実践可能。
④立って机にもたれた姿勢で:軽く前傾し、膝を曲げて肛門を締める。日常動作に最も近い状態で鍛えられる。
呼吸を止めずに自然に行うことが大切です。効果が現れるまで3か月程度かかるため、毎日コツコツと続けましょう。
膀胱を温める
体の冷えは膀胱の血流を悪化させ、頻尿の原因となります。下腹部を温めるには、腹巻やカイロが効果的です。足元の冷えは、レッグウォーマーや厚手の靴下で対策できます。
40度前後のお湯に10〜15分ほど足をつける足湯もおすすめです。入浴の際は、湯船にゆっくり浸かって体を芯から温めましょう。
ストレスを溜めないようにする
ストレスは膀胱を過敏にし、頻尿の原因となります。リラックスできる時間を毎日少しでも確保しましょう。深呼吸をする、好きな音楽を聴く、軽い運動をするなど、自分に合った方法でストレスを軽減することが大切です。
良質な睡眠を確保することも、ストレス軽減と夜間頻尿の改善につながります。
弾性ストッキングを履く
夜間頻尿の原因のひとつに、夜間多尿があります。日中に立っていることで下肢に水分が貯留し、夜横になることでその水分が体内に戻り、尿量が増えるというメカニズムです。
この対策として、日中に弾性ストッキングを履くことが効果的です。弾性ストッキングは、足に適度な圧力をかけることで、下肢への水分貯留を防ぎます。
弾性ストッキング以外にも、夕方に30分以上の両脚上げ運動を行うことで、下肢に溜まった水分を体に戻すことができます。
まとめ
頻尿の原因は、過活動膀胱や膀胱炎などの疾患から、水分の摂りすぎや体の冷えといった生活習慣まで多岐にわたります。まずは排尿日誌を付けて自分の状態を把握し、必要に応じて泌尿器科を受診して原因を特定することが大切です。
この記事で紹介した膀胱訓練、骨盤底筋トレーニング、適切な水分管理、体を温める工夫などのセルフケアは、頻尿の改善に効果が期待できます。すべてを一度に始める必要はないため、できることから少しずつ取り入れて継続してみてください。
ただし、これらの対策を試しても症状が改善しない場合や血尿・痛みなど、ほかの症状をともなう場合は、重篤な疾患が隠れている可能性もあります。早めに専門医を受診することをおすすめします。