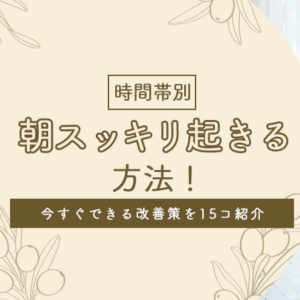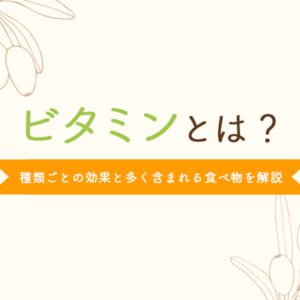
サジーコラム
Column
スーパーフードとは?効果や注目される理由・スーパーで買える食品を紹介
サジー 栄養 健康 美容 2025.04.16

チアシードやキヌア、アサイーといった海外のスーパーフードを耳にする機会が増えてきました。実は、これらは高い栄養価を持ち、忙しい現代人の健康を支える頼もしい存在です。
さらに、納豆や味噌など、日本の食卓になじみ深い伝統食品のなかにも、世界から注目されるスーパーフードがあります。
本記事では、スーパーフードの基本から種類ごとの特徴、そして日常生活に無理なく取り入れるコツまで、わかりやすく紹介します。
スーパーフードとは?
スーパーフードという言葉は、1980年代のアメリカやカナダで生まれました。2004年には医師スティーブン・プラットの著書で紹介され「健康によい栄養素を豊富に含み、多くは低カロリーな食品」として広まりました。
日本スーパーフード協会は、次の2点を定義としています。
● 栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高いこと
● 特定の栄養成分が突出して多いこと
つまり、スーパーフードは食品とサプリメントの中間のような存在です。少量でも効率よく栄養をとれるのが特徴で、毎日の食事に取り入れやすい食品といえます。
スーパーフードが注目される理由
忙しい毎日で栄養バランスのとれた食事が難しいなか、効率よく栄養をとれるスーパーフードは大きな人気を集めています。
また、健康志向の人々が取り入れたことで注目度が高まり、とくに抗酸化作用の強い食品はエイジングケアの観点から人気です。
さらに、キヌアやモリンガのように環境負荷の少ない作物も多く、持続可能な社会に合った食品として評価されています。
このように、栄養価の高さ、手軽さ、環境配慮という3つの観点から、スーパーフードは現代社会のニーズに合致した食品として注目を集めているのです。

スーパーフードの主な種類13選
世界には数多くのスーパーフードが存在しますが、ここではとくに注目度の高い13種類を紹介します。それぞれの特徴や栄養価、簡単な取り入れ方を知って、食生活に役立ててください。
サジーベリー
サジーベリーはユーラシア大陸に自生する果実で、古くから「生命の果実」と呼ばれてきました。ギリシャ神話やチンギスハンの遠征にも登場するなど、歴史ある食品です。
約200種類もの栄養素を含み、とくにビタミンCや鉄分が豊富です。そのため、美容や健康維持を意識する人から支持されています。
酸味が強いため、ジュースにして飲むのが一般的ですが、水やお湯で割ったり、はちみつや果汁を加えると飲みやすくなります。
アサイーベリー
アサイーベリーはブラジル・アマゾン原産の果実で、先住民に長く親しまれてきました。濃い紫色の色素アントシアニンを多く含み、強い抗酸化作用で若々しさを保ちたい人に人気です。
さらに鉄分、食物繊維、カルシウム、ビタミンEも豊富。とくに鉄分は女性に不足しやすく、毎日の元気を支えてくれます。
生の輸入が難しいため、冷凍ピューレやパウダーで流通しており、アサイーボウルが代表的な食べ方です。スムージーやヨーグルトに混ぜても手軽に楽しめます。
マキベリー
マキベリーは、チリ南部パタゴニア地方に自生する希少なベリーで、古くから薬用植物として利用されてきました。
最大の特徴は強い抗酸化力です。アントシアニンの一種デルフィニジンを豊富に含み、その量は赤ワインやブルーベリーの10倍以上ともいわれています。ビタミンCや鉄分、カリウム、食物繊維も含まれ、美容や健康維持を意識する人に人気です。
生では流通しにくいため、主にフリーズドライパウダーとして販売されています。スムージーやヨーグルトに混ぜれば、鮮やかな紫色と甘酸っぱい風味を楽しめます。
ゴジベリー(クコの実)
ゴジベリーは中国原産の果実で、日本でも「クコの実」として薬膳料理などに用いられてきました。3000年以上の歴史を持ち「不老長寿の薬」と呼ばれることもあります。
ビタミンCや鉄分、食物繊維、18種類のアミノ酸を含み、とくに目の健康を支えるゼアキサンチンが豊富です。βカロテンやポリフェノールも含まれ、美容やエイジングケアを意識する人に人気があります。
食べ方は多様で、ドライフルーツとしてそのまま、薬膳スープやお茶、スムージーやヨーグルトのトッピングなどに活用できます。
アセロラ
アセロラは西インド諸島原産の果実で、日本では沖縄でも栽培されています。「ビタミンCの王様」と呼ばれ、レモンの30倍以上のビタミンCを含むのが特徴です。
ビタミンCはコラーゲン生成を助け、美容や健康維持に役立ちます。さらにクエン酸やポリフェノールも含まれ、鉄分吸収のサポートにもつながります。
酸味が強いためジュースとして利用されることが多く、冷凍果実やパウダーも流通しています。スムージーやヨーグルトに混ぜたり、ゼリーやシャーベットに使ったりするのもおすすめです。
ナツメ
ナツメは中国北部原産の果実で「一日三棗で百歳まで老けない」といわれるほど健康によい食材として親しまれてきました。
ビタミンC、鉄分、カリウム、食物繊維などを豊富に含み、とくに鉄分は活力を、カリウムは水分バランスを整えるのに役立ちます。中医学では「気」を補う食材とされ、活力や美容ケアにも利用されてきました。
一般的には干しナツメとして流通し、そのまま食べるほか、お茶や薬膳料理、スープに加えるのが一般的です。甘露煮やジャムにして楽しむこともできます。
キヌア
キヌアは南米アンデス原産の穀物で、インカ帝国時代から「穀物の母」と呼ばれてきました。
最大の特徴は、必須アミノ酸9種類をすべて含む完全タンパク質であることです。植物性食品でありながら、肉や魚に匹敵する良質なタンパク質を摂取できます。鉄分やカルシウム、マグネシウムなどのミネラルも豊富で、食物繊維も多く含まれています。
低GIで腹持ちがよく、グルテンフリーのためダイエットや小麦アレルギー対応にも適しています。炊き込みご飯やサラダ、スープなどに加えると、プチプチした食感が料理のアクセントになります。
チアシード
チアシードはメキシコ原産のシソ科植物「チア」の種子で、古代アステカでは戦士の栄養源として使われてきました。「チア」はマヤ語で「強さ」を意味します。
水に浸すと約10倍に膨らみジェル状になるのが特徴で、少量でも満腹感が得られるため体重管理を意識する人に人気です。膨潤した部分はグルコマンナンという水溶性食物繊維で、スッキリをサポートする働きがあります。
栄養面ではオメガ3脂肪酸、タンパク質、カルシウム、鉄分、マグネシウムなどが豊富です。とくにオメガ3脂肪酸は現代人に不足しやすく、健康維持に役立ちます。食べ方は簡単で、水に浸してヨーグルトやスムージーに混ぜるのが一般的です。
ビーツ
ビーツは地中海沿岸原産の根菜で、鮮やかな赤紫色と自然な甘みが特徴です。ヨーロッパでは「食べる輸血」と呼ばれるほど栄養価の高い野菜として親しまれてきました。
色素成分のベタシアニンやベタキサンチンには強い抗酸化作用があり、美容や健康維持に役立ちます。葉酸、鉄分、カリウム、ビタミンCも豊富で、とくに硝酸イオンはコンディションアップをサポートします。
生でスライスしてサラダに、ジュースやスムージーにするほか、茹でる・蒸す・焼くなど加熱調理でも楽しめます。スープやピクルスにすると彩りもよくおすすめです。
ブロッコリースプラウト
ブロッコリースプラウトは発芽から3日目の新芽です。
最大の特徴は、「デトックスの王様」とも呼ばれているスルフォラファンを豊富に含むことです。成熟したブロッコリーの約20倍にのぼり、体内の解毒や抗酸化に役立つとされています。
近年は、ピロリ菌の抑制や花粉症の軽減、肝機能サポートなど多様な効果も注目されています。ビタミンCや葉酸などの栄養素も含まれ、健康維持に幅広く貢献します。
食べ方は「生でよく噛む」のがポイントです。サラダやサンドイッチ、料理のトッピングに手軽に使え、忙しい人にも取り入れやすい食品です。
スピルリナ
スピルリナは藍藻類の一種で「地球最古の植物」とも呼ばれ、古くから食用とされてきました。特徴は、植物でありながら約60〜70%がタンパク質で、必須アミノ酸をすべて含む点です。
消化吸収率も95%と高く、ビタミンB群や鉄分、カルシウムなど50種類以上の栄養素をバランスよく含みます。青い色素フィコシアニンやクロロフィルも豊富で、抗酸化や野菜不足の補いに役立ちます。
流通形態はパウダーやタブレットが一般的で、スムージーやヨーグルトに混ぜたり、パンやお菓子に加えて摂取できます。独特の風味があるため、少量から始めるのがおすすめです。
モリンガ
モリンガは「奇跡の木」と呼ばれるワサビノキ科の植物で、葉から根まで利用できる貴重な食材です。インドや東南アジアで広く栽培され、栄養失調の改善にも役立つとして国際機関からも注目されています。
特徴は90種類以上の栄養素を含むことです。必須アミノ酸をはじめ、カルシウムや鉄分、ビタミン類、ポリフェノール、食物繊維などがバランスよく含まれ、抗酸化作用も期待できます。
主にパウダーやお茶として流通し、抹茶のような色とほのかな苦みがあります。お茶として飲むほか、スムージーやヨーグルトに混ぜたり、青汁感覚で取り入れるのもおすすめです。
カカオ
カカオは中南米原産の常緑樹で、古代から「神々の食べ物」と呼ばれてきました。種子はチョコレートの原料であり、栄養価の高さでも注目されています。
カカオニブやカカオパウダーにはポリフェノールが豊富で、赤ワインの2倍以上といわれる強い抗酸化作用があります。
さらにテオブロミンによるリラックスや集中力アップの効果、血流改善や動脈硬化予防の働きも期待されます。鉄分やマグネシウムなどのミネラル、食物繊維も含まれます。
カカオニブはそのまま食べるほか、ヨーグルトやシリアルのトッピングに最適です。カカオパウダーはココアやスムージー、製菓に使えます。
日本にもスーパーフードが!代表的な食材・食品5選
日本の伝統食品にも、世界が注目する優れた食品があります。「ジャパニーズスーパーフード」と呼ばれるこれらは、長く日本人の健康を支えてきた実績があり、栄養学的にも非常に優秀です。
納豆
納豆は大豆を納豆菌で発酵させた日本の伝統食品です。
良質なタンパク質に加え、ビタミンK2や大豆イソフラボン、食物繊維を含みます。とくに注目されるのがナットウキナーゼで、血流をサポートする働きが期待されています。腸内環境を整えるプロバイオティクス作用もあり、美容や免疫維持にも役立ちます。
食べ方はご飯にかけるのが定番ですが、オムレツやパスタ、サラダに加えるなどアレンジも自在です。ただし、血液をサラサラにする薬を服用中の方は注意が必要です。
味噌
味噌は大豆を麹菌や乳酸菌などで発酵させた、日本を代表する調味料です。飛鳥時代から「医者いらず」と親しまれ、健康効果の高い食品とされています。
発酵によりタンパク質が分解され消化吸収がよくなるほか、新たな栄養素も生まれます。良質なタンパク質、必須アミノ酸、ビタミンB群、食物繊維、植物性乳酸菌などを含みます。
もっとも身近なのは味噌汁ですが、炒め物や漬物、洋風料理の隠し味にも使える万能調味料です。毎日の食事に取り入れやすいスーパーフードといえるでしょう。
甘酒
甘酒は米麹や酒粕から作られる日本の伝統的な甘味飲料で「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養価が高い食品です。江戸時代には夏バテ防止の飲み物として親しまれてきました。
米麹の甘酒は、麹菌がデンプンを分解することで砂糖を加えなくても自然な甘みを持ちます。ブドウ糖は活力をサポートし、ビタミンB群や必須アミノ酸、オリゴ糖、食物繊維も豊富です。
そのまま温めたり冷やしたりして飲めるほか、スムージーやヨーグルトに混ぜても楽しめます。お菓子作りの甘味料代わりに使えるのも魅力です。
海藻
海苔や昆布、わかめ、ひじきなど、海藻は日本の食文化に欠かせない食材です。最大の特徴は海由来のミネラルが豊富なこと。ヨウ素やカルシウム、鉄分、マグネシウムなどを効率よく補給できます。
海苔にはビタミンB12やタンパク質、わかめやひじきにはカルシウム、昆布には旨味成分グルタミン酸が含まれるなど、それぞれに特長があります。さらにアルギン酸やフコイダンといった成分が食習慣のサポートにも関わります。
食べ方は手巻き寿司やおにぎり、味噌汁、煮物、サラダ、スムージーに加えるのが手軽でおすすめです。
緑茶・抹茶
緑茶と抹茶は日本を代表する飲み物で、奈良時代には薬として用いられていました。
最大の特徴はカテキンを豊富に含むことです。強い抗酸化作用で体調維持にも役立つとされています。
さらに、テアニンによるリラックス効果とカフェインの覚醒作用の組み合わせで、心身のバランスを整えます。
抹茶は茶葉を丸ごと摂取するため、ビタミンEやβカロテン、食物繊維まで取り入れられる点が特徴です。日常的に飲む緑茶はもちろん、抹茶ラテやスイーツに活用するのもおすすめです。
まとめ
スーパーフードは健康や美容を支える強い味方です。海外由来のアサイーベリーやチアシード、日本の納豆や味噌など、種類ごとに異なる栄養と魅力があります。
ただし、万能薬ではなく、バランスの取れた食事の一部として取り入れることが大切です。無理をせず、楽しみながら続けることで、体調や目的に合った効果を実感しやすくなります。
数あるスーパーフードのなかでも、おすすめなのがサジーベリーです。サジーベリーを使った「サジーワン」は、鉄分やビタミン類、アミノ酸など、毎日の暮らしにうれしい成分がバランスよく含まれています。
健康的な生活を目指すなら、日々の習慣にサジーワンを取り入れてみてはいかがでしょうか。