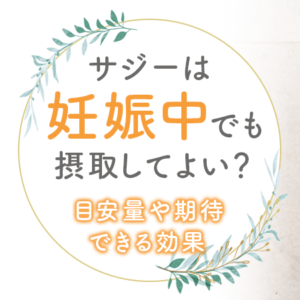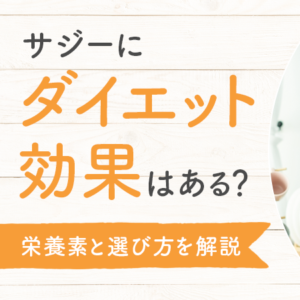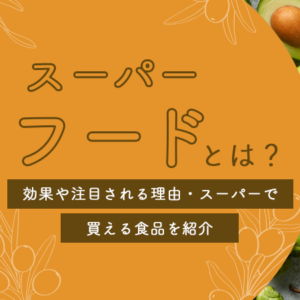
サジーコラム
Column
女性がイライラする時の原因は?40代から見直したい食生活と解消法
美容 2025.05.08

仕事や家事、育児に追われる毎日の中で、些細なことにイライラしてしまうことはありませんか?そのイライラ、実は心だけでなく体からのサインかもしれません。
とくに40代女性は、ホルモンバランスの変化や慢性的な疲労が重なり、感情のコントロールが難しくなる時期です。心と体の両面からアプローチして、穏やかな毎日を取り戻しましょう。
本記事では、イライラする原因を深掘りしながら、40代からとくに意識したい食生活の見直しポイントや、今日からできる解消法をご紹介します。
女性がイライラする時とは?
40代の女性は、人生の中でもとくに多忙な時期を迎えています。仕事ではキャリアの中核を担い、家庭では子育てや家事に追われ、さらに親の介護が始まる方もいます。こうした複数の役割を同時にこなすなかで、心身ともに余裕がなくなり、イライラしやすい状態に陥ってしまうのです。
子育て世代の女性にとって、イライラは日常茶飯事といっても過言ではありません。朝は家族の朝食準備と自分の支度を同時進行し、仕事では責任ある立場でプレッシャーを感じ、帰宅後は夕食作りや子どもの宿題チェックなど、やることが山積みです。
とくに30代男女や40代女性などの子育て世代は、慢性的に疲れを感じている人も多いでしょう。ゆっくりと疲れを癒す暇がないほど時間に追われる毎日が、心の余裕を奪っているのです。
日常生活に潜むイライラのタネは、いたるところにあります。職場の人間関係、経済的な不安、配偶者やパートナーとのすれ違い、家事の分担への不満など、小さなストレスが積み重なることで大きなイライラへと変化していきます。

イライラする時の主な原因
イライラを引き起こす原因はひとつではありません。心理的な要因から身体的な問題まで、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。
ストレス
ストレスは、イライラを引き起こす最も代表的な原因です。厚生労働省の令和6年度過労死等防止対策白書によると、仕事にストレスを感じている人は約82%にものぼります。
ストレスを感じると、交感神経の働きが優位になり、血圧が上昇し心拍数が増えて常に緊張状態に陥ります。この状態が続くと集中力が欠如したり、不安感や抑うつ状態にさいなまれたりします。
コルチゾールやノルアドレナリンなどのストレスホルモンが体内で放出され、精神状態のバランスが崩れ、さらにストレスを感じやすくなる負のスパイラルに陥りやすくなります。
40代女性の場合、職場の人間関係、経済的不安、子育ての悩み、配偶者とのコミュニケーション不足、親の介護問題など、多方面からのストレスに晒されています。
出典:厚生労働省「令和6年度過労死等防止対策白書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/gian_hokoku/20241011karoushigaiyo.pdf/$File/20241011karoushigaiyo.pdf)
ホルモンバランスの乱れ
女性特有のイライラの原因として、ホルモンバランスの乱れが挙げられます。これは本人の意思とはまったく関係なく生じるもので、月経周期、妊娠、出産、更年期といったライフステージにおいてとくに顕著に現れます。
月経前になると普段なら気にならないことでもカッとなりイライラする「月経前症候群(PMS)」を経験する女性は少なくありません。40代女性にとってとくに注意が必要なのは更年期の兆候です。女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少することで、イライラ、不安感、気分の落ち込みなど、精神面での変化を感じやすくなります。
睡眠不足
睡眠不足は、イライラを誘発する大きな要因です。アメリカの大学の研究結果では、睡眠時間が少ない人は十分な人に比べて怒りの感情が出やすくなることが明らかになっています。
睡眠は脳の機能回復、記憶の整理、感情の処理など、心身の健康維持に欠かせません。睡眠不足に陥ると脳の働きが鈍り、集中力やストレスへの耐性が低下します。人は就寝中に感情の処理を行うと言われていますが、睡眠不足が続いて処理が追いつかないと、イライラなどの感情が記憶として残ってしまうのです。
慢性的な疲れ
慢性的な疲労は、イライラの引き金となります。とくに脳疲労が続くと、幸せホルモンともいわれるセロトニンの分泌が低下し、感情のコントロールができなくなります。
大正製薬の調査によれば、疲れてイライラしがちな人の約8割が「慢性的に疲れている」と回答しています。40代女性の場合、仕事での責任が重くなる年代であると同時に、家事や育児、場合によっては親の介護も加わり、休息する時間を十分に取れないことが多くあります。
空腹や暴食
空腹や暴食も、イライラを引き起こす要因のひとつです。空腹を感じると、脳は栄養不足だと判断し、血糖値を上げる働きのあるアドレナリンやノルアドレナリンを分泌します。ノルアドレナリンが分泌されると興奮状態となり、怒りや焦燥感を引き起こしやすくなるのです。
一方で、空腹状態からいきなり大量の食事を摂ると、急激に血糖値が上昇し、その反動で血糖値が急降下する「血糖値の乱高下」が起こります。この乱れが精神状態を不安定にし、イライラしやすくします。とくにストレスがかかると甘いものを無性に食べたくなりますが、摂りすぎは血糖値の急上昇と急降下を招き、かえってイライラを悪化させる可能性があります。
作業量の多さ
仕事や家事など、日々の膨大な作業量も気分を沈ませ、ストレスを誘発させる原因となります。40代女性の多くは、職場で中堅からベテランの立場にあり、責任ある仕事を任されています。同時に家庭では「母親」「妻」「娘」といった複数の役割を担い、朝の支度から夜の片付けまで休む暇がありません。
やることリストが終わらないうちに新しいタスクが追加され、常に何かに追われているような感覚に陥りやすいのです。すべてを一人で抱え込まず、家族や職場の同僚に協力を求めることも大切です。
栄養不足や食生活の乱れ
必要な栄養の不足も、イライラを誘発すると考えられます。40代女性は、仕事や家庭の両立で忙しく、自分の食生活が後回しになりがちです。朝食を抜いたり、ランチはコンビニで済ませたり、夜は子どもの残り物や冷凍食品で簡単に済ませることも多いでしょう。
タンパク質が不足すると、感情伝達物質 の生成が減少し、ストレス耐性が低下します。鉄分の不足は、やる気や集中力の低下を引き起こします。とくに女性は月経により鉄分が失われやすく、慢性的な鉄不足に陥りやすいのです。
ビタミンB群が不足すると、不安、イライラ、焦燥、疲労感を感じやすくなります。ビタミンB群は、疲労感の軽減や神経伝達物質の生成に重要な栄養素です。カルシウムが不足すると、自律神経の乱れによるストレスやイライラが生じやすくなります。また、糖質の過剰摂取は血糖値の乱高下を引き起こし、イライラを感じやすくなるため注意が必要です。
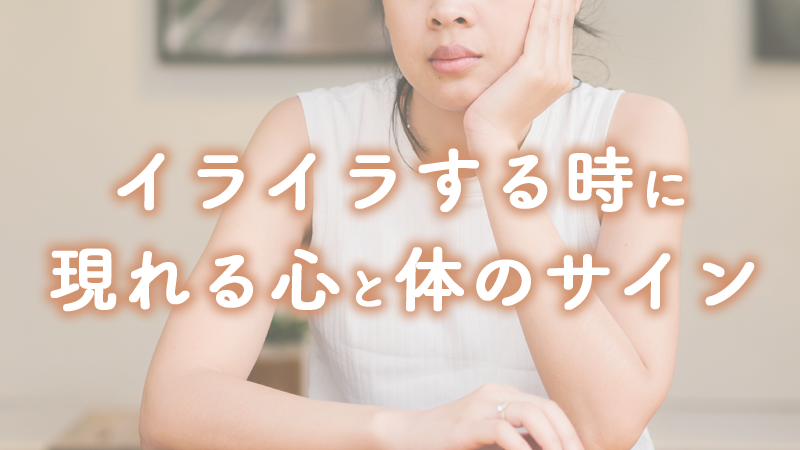
イライラする時に現れる心と体のサイン
イライラを放置しておくと、心と体にさまざまな負担がかかります。初期段階では些細な不調として現れますが、放置することでより深刻な状態に発展する可能性があります。
自律神経の乱れが引き起こす不調
イライラが与える悪影響のひとつに、自律神経の不調が挙げられます。自律神経とは、呼吸や体温調節、消化、排泄など、基本的な生命活動を続けるために重要な役割を担っています。
ストレスを感じると交感神経の働きが優位になり、副交感神経とのバランスが崩れます。自律神経の不調で引き起こされる代表的な症状は、倦怠感、不眠、息切れや動悸、手足のしびれ、めまいやふらつき、肩こり、頭痛や腹痛、慢性的な便秘や下痢など、多岐にわたります。
食欲がわかない・食べすぎなどの食欲不振
イライラしているときには、食欲の変化が見受けられる場合があります。ストレスが自律神経に伝達され均衡が崩れると、胃の働きに影響が出てしまいます。胃酸の過剰分泌による胃痛を引き起こしたり、消化や吸収がしづらくなるために食欲が低下する可能性があります。
一方で、ストレスによって逆に食欲が増進し、暴飲暴食に走るケースもあります。食欲の乱れは栄養バランスの偏りを招き、それがさらにイライラを悪化させるという悪循環に陥りやすくなります。
不眠に悩まされる
イライラが原因で精神的に負担がかかり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなるなど、不眠の症状を引き起こす可能性があります。ストレスを感じるとリズムが乱れ、脳が興奮状態となり深く休息できなくなります。
このような慢性的な不眠が続くと、集中力や記憶力が低下し、日中のパフォーマンスに影響が出ます。イライラがさらに増幅するという負のサイクルに陥ってしまうのです。
うつなど心の病気
イライラした状態が長期的に続くと、うつなどの心の病につながるリスクがあります。イライラは単なる感情的な問題に留まらず、放置するとうつ病や適応障害、自律神経失調症といった心の病に発展する可能性があるのです。
一日を通して気分が落ち込んだり、物事が億劫になったり、今まで楽しかったことに興味が持てなくなるような症状が現れた場合、うつ病などの心の病を引き起こすおそれがあります。症状が長期間続く場合や、日常生活に支障をきたすほどの状態になった場合は、医療機関への相談を検討することが大切です。

イライラする時に心を楽にする方法
イライラを感じたとき、すぐに実践できる解消法を知っておくことは、心の健康を保つうえで非常に重要です。
深呼吸する
イライラしたときにすぐに実践できる方法として、深呼吸があります。深呼吸には交感神経と副交感神経のバランスを整え、副交感神経の働きを優位にし、新鮮な酸素を全身にいきわたらせる効果が期待できます。
具体的には、腹式呼吸を意識してみましょう。5秒程度かけて鼻から息を吸い込み、その倍の10秒ほどかけてゆっくりと口から息を吐き出します。この呼吸を5回ほど繰り返すだけで気持ちがリセットされ、落ち着きを取り戻せます。職場でも家庭でも、場所を選ばずにできるのが深呼吸の大きなメリットです。
笑う
笑うことは、ストレスの軽減に非常に効果的です。笑うとドーパミン、セロトニン、オキシトシンなどのいわゆる幸福ホルモンが分泌され気分を高めます。またストレスホルモンのコルチゾールの分泌が抑制されるため、リラックスした状態を保てるでしょう。
笑う機会を増やすには、お笑い番組を見る、面白い動画を探す、友人とのおしゃべりを楽しむなど、日常生活の中に笑いを取り入れる工夫をしましょう。最初は作り笑いでも、笑顔を作るだけで脳は「楽しい」と錯覚し、幸福ホルモンの分泌が促されます。
こまめに休憩を取る
業務や作業の合間に、意識的にこまめな休息を取ることも大切です。緊張状態が長引くと、脳に大きな負担がかかります。5分程度の短い休憩でも立ち上がってストレッチをする、窓の外の景色を見る、お茶を飲んでほっと一息つくだけで、脳はリフレッシュされます。
タイマーを使って、1時間に1回は立ち上がる習慣をつけるなど、意識的に休憩を取り入れましょう。休憩は怠けではなく、パフォーマンスを維持するための必要な時間なのです。
誰かに相談する
気の置けない人との会話を楽しむことも、ストレス軽減につながります。実際に言葉に出すと、相手からの思いがけない意見やアドバイスで解決や好転につながる場合もあります。
また、自分の感情を人に話すことで気持ちが整理されたり、相手の視点からアドバイスをもらえたりすることがあります。ただ話すだけで、心のつかえがすっと取れることもあるでしょう。
仕事の話を身近な人に言いづらい場合は、外部相談窓口やカウンセラーなど専門家に話をするのもひとつの方法です。
イライラの原因を書き出す
あえてイライラの原因を書き出してみる方法もあります。名古屋大学の研究によると、怒りの感情の内容を紙に書いて捨てることで、気持ちが鎮まる効果があることが実証されています。
ノートや紙に「今、私は何にイライラしているのか」を箇条書きで書き出してみましょう。書き出すことで、漠然としたイライラが具体化され「実はこれが一番のストレスだったんだ」と気づくこともあります。書いた紙を破って捨てることで、心理的なカタルシスを得られます。
自然のなかで心を整える
森や緑など自然と親しむ時間を増やすことでも、ストレスを軽減できます。森の木々からは、心身をリフレッシュさせるフィトンチッドという成分が発散されています。
また、外に出て日光を浴びることも重要です。日光を浴びると神経伝達物質であるセロトニンが分泌され、心身をリラックスさせる効果があります。近くの公園での散策など、気軽に楽しめるものから始めるとよいでしょう。
好きなことをする
イライラしたときには、好きなことや楽しいと思うことをするのもおすすめです。趣味に打ち込むことで、余計なことを考える時間が減り、イライラした気持ちから離れられます。
週に一度、30分でも自分のための時間を作ることは、心の健康を保つうえで非常に重要です。自分のできる範囲で、無理なく楽しめることを探してみてください。
ゆっくりと休む
ゆっくり休むことも、ストレスを軽減するためには重要です。疲れを感じるときは体が休息を求めているサインです。早めに布団に入る、週末の午前中は何も予定を入れずにゆっくり過ごす、お気に入りのカフェでのんびりするなど、自分にとって心地よいと感じる方法で休むことが大切です。
思い切ってゆっくりと休み、力を溜めてからまた頑張りましょう。休息は自分へのご褒美であり、次の活動のためのエネルギー補給なのです。
食生活を工夫する
疲労軽減やストレス解消に、栄養素の摂取はおすすめの方法です。食事にはゆっくりと時間をかけ、よく噛むことも心がけましょう。よく噛むと脳内の扁桃体の活動が抑えられ、ストレスを感じにくくなります。
イライラ軽減に効果的な栄養素として、ビタミンB群、ビタミンC、トリプトファン、マグネシウム、カルシウムなどが挙げられます。ビタミンB群は疲労感の軽減や神経伝達物質の生成に重要です。ビタミンCはストレス耐性を高めます。トリプトファンやマグネシウムは、幸福ホルモンであるセロトニンの分泌を促し、心を落ち着かせます。
栄養バランスのとれた食事を、ゆっくりとよく噛んで食べることが、イライラ軽減の基本となります。
女性におすすめのイライラ予防習慣
一時的な解消法も大切ですが、日常的にイライラしにくい体を作ることも重要です。
体と心を一緒に整える漢方を味方に
東洋医学の観点から、漢方が心身の不調にアプローチし、イライラの予防につながることがあります。漢方は体全体のバランスを整えることで、根本的な改善を目指します。
イライラのタイプによって、適した漢方薬は異なります。たとえば、イライラしやすく、のぼせやほてりを感じる方には「加味逍遙散」、不安感が強く眠れない方には「酸棗仁湯」、ストレスで胃腸の調子が悪い方には「半夏厚朴湯」などが使われることがあります。
ただし、漢方薬は体質や症状によって適切なものが異なるため、自己判断ではなく、漢方薬局や漢方を扱う医療機関で相談することが大切です。
不足しがちな鉄分・ミネラル・ビタミンをしっかり補う
イライラ予防のために、とくに女性が不足しがちな鉄分、ミネラル、ビタミンを積極的に補給することが重要です。これらの栄養素は、精神安定やストレス耐性を高めるうえで欠かせません。
鉄分は、やる気や集中力を保つために必要な栄養素です。女性は月経により鉄分が失われやすく、慢性的な鉄不足に陥りやすい傾向があります。ビタミンB群は、神経の働きを正常に保ち、ストレス耐性を高めます。ビタミンCは、ストレスホルモンの生成に関わり、ストレス耐性を高めます。また、鉄分の吸収を助ける働きもあります。
マグネシウムは神経の興奮を抑え、リラックス効果をもたらします。カルシウムも神経の興奮を抑える働きがあります。
しかし、忙しい40代女性にとって、毎日の食事でこれらの栄養素を完璧にバランスよく摂取することは簡単ではありません。そんなときには、栄養補助食品やサプリメントを上手に活用することもひとつの方法です。毎日の食事を基本としながら、足りない部分を補助食品で補うことで、心身のバランスを整え、イライラしにくい体を作ることができます。
まとめ
イライラする原因は、ストレス、ホルモンバランスの乱れ、睡眠不足、慢性的な疲れ、空腹や暴食、作業量の多さ、栄養不足や食生活の乱れなど、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。とくに40代女性は、仕事と家庭の両立、子育て、更年期の兆候など、心身ともに負担がかかりやすい時期です。
イライラを放置すると、自律神経の乱れ、食欲の変化、不眠、さらにはうつなどの心の病に発展する可能性もあります。深呼吸や笑うこと、こまめな休憩、誰かに相談するなど、日常生活の中ですぐに実践できる解消法を取り入れることが大切です。
また、漢方を取り入れたり、不足しがちな鉄分・ミネラル・ビタミンをしっかり補うなど、長期的な予防習慣を身につけることでイライラしにくい心身を作ることができます。とくに食生活の見直しは、イライラ予防の要となります。
健康的な暮らしを送りたい方、毎日を穏やかに過ごしたい方は、体に必要な栄養をしっかり補給することから始めてみませんか。
自分を大切にすることは、家族や周りの人を大切にすることにもつながります。今日から少しずつ、心と体を整える習慣を取り入れて、笑顔で過ごせる毎日を手に入れましょう。