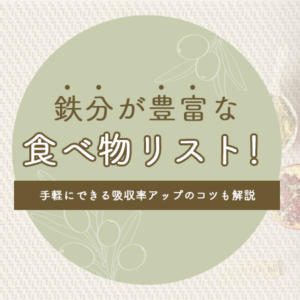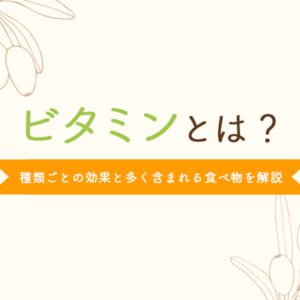
サジーコラム
Column
鉄分を簡単に摂る方法!今日からできる&ムリなく続く習慣8つを紹介
サジー 栄養 2024.12.22
鉄分は、健康を保つうえで欠かせない重要な栄養素です。しかし、日本人の多くが鉄分不足に陥っているとされています。とはいえ、ただ多く摂取すればよいというわけではありません。

大切なのは「どれだけ摂るか」よりも「いかに効率よく吸収するか」です。鉄分は、体にしっかり吸収されてこそ、はじめてその効果を発揮します。
この記事では、鉄分の基礎知識とともに、すぐに実践できる8つの習慣を解説します。鉄分を効率よく取り入れたい方は、ぜひ参考にしてください。
今日からできる!鉄分を簡単に摂る8つの方法
鉄分は不足しがちな栄養素ですが、特別な調理や難しい知識がなくても、ちょっとした工夫で効率よく摂取できます。調理器具の選び方や食材の組み合わせ、食べ方を意識するだけで、毎日の食事で無理なく鉄分を補うことが可能です。
ここでは、すぐに実践できる8つの具体的な方法を紹介します。
1:鉄鍋や鉄フライパンで調理する
もっとも簡単で効果的なのが、日々の調理器具を「鉄製」に変える方法です。鉄鍋や鉄フライパンで加熱調理を行うと、微量の鉄分が食材に溶け出し、自然と鉄分を補給できるメニューに早変わりします。
とくに、トマトやレモン、酢などの酸味のある食材と一緒に使うと、鉄の溶出量が増え、体への吸収率もアップするためおすすめです。
2:食事に鉄分が豊富な主菜や副菜を加える
毎日の食事で鉄分を効率よく摂るには、食材選びが大切です。少し意識するだけで、鉄分の摂取量に大きな差が生まれます。
たとえば、鉄分補給に最適な1品として「レバニラ炒め」があります。鉄分を豊富に含むレバーに加え、ビタミンCが含まれるニラを一緒に調理することで、鉄の吸収率を高める効果が期待できるでしょう。
副菜には、小松菜やほうれん草などの緑黄色野菜を使ったサラダやおひたしがおすすめです。鉄分に加えて、食物繊維やビタミン類も一緒に摂れるため、美容や健康維持にも役立ちます。
3:鉄分の吸収率を高める食品を摂る
せっかく鉄分を摂取しても、体にしっかり吸収されなければ意味がありません。そこで重要になるのが、鉄分の吸収を助ける栄養素との組み合わせです。
鉄分と相性のよい食品について、詳しく見ていきましょう。
動物性タンパク質
動物性たんぱく質に含まれるアミノ酸は、植物由来の非ヘム鉄の吸収を高める働きがあります。
これは、たんぱく質が胃の働きを活発にし、鉄分を体に吸収しやすい状態に整えてくれるためです。そのため、野菜や豆類を中心とした食事でも、少量の肉や魚を加えることで、鉄の吸収効率を高められます。
ただし、脂肪分が多い食品を摂りすぎると、カロリーオーバーや生活習慣病のリスクにつながる可能性があります。赤身の肉や脂肪の少ない魚を選び、バランスよくたんぱく質を取り入れましょう。
ビタミンC
ビタミンCには、鉄分の吸収を助ける働きがあります。たとえば、ほうれん草の炒め物にレモン汁を加えるだけで、体への吸収効率が大きく変わります。
毎日の食事に、ビタミンCを豊富に含む果物や野菜を上手に取り入れることで、手軽に鉄分の吸収を高める習慣をつくれます。
クエン酸
酢や梅干し、レモンなどに含まれるクエン酸にも、鉄分の吸収を高める効果があります。さらに、クエン酸は体内のエネルギー産生を助け、疲労回復にも役立つとされています。
酢を使ったドレッシングや、梅干しを加えた和え物などは、手軽にクエン酸を取り入れられるのでおすすめです。酸味を上手に活用すれば、食卓にさわやかなアクセントが加わり、毎日の食事がより楽しくなります。
4:鉄分の吸収を阻害する食品を控える
鉄分を効率よく体に取り込むためには、吸収を妨げる食品や飲み物を控えることも大切です。以下に挙げるようなものは、できるだけ摂取のタイミングや量に気をつけましょう。
タンニン
タンニンは、緑茶や紅茶、コーヒーに含まれるポリフェノールの一種です。この成分は鉄分の吸収を妨げる働きがあるため、鉄分をしっかり取り入れたい場合は、飲むタイミングに注意が必要です。 食後すぐに飲むのは避け、食前や食間に摂るようにするとよいでしょう。
リン
リンは、丈夫な骨や歯をつくるために欠かせない栄養素ですが、過剰に摂取すると体内での鉄分の吸収が妨げられる可能性があります。
とくに注意したいのが、加工食品やインスタント食品に多く含まれているリン酸塩やリン酸ナトリウムなどの食品添加物です。手軽に食べられる反面、頻繁に摂取していると知らないうちにリンを過剰に取り込み、鉄分不足を引き起こす原因になることがあります。
鉄分をしっかり取り入れるためにも、食事のバランスに気を配りながら、加工食品の摂りすぎを控えることが大切です。
フィチン酸
フィチン酸は、玄米やごま、とうもろこしなどに多く含まれている成分です。抗酸化作用がある一方で、鉄分の吸収を妨げる性質もあります。
栄養をしっかり取り入れたい場合は、玄米を食べる頻度を週に数回に抑えたり、白米とブレンドして炊いたりするなど、無理のない工夫を取り入れることがおすすめです。
シュウ酸
シュウ酸は、野菜に含まれるえぐみやアクの原因となる成分です。ただし、水に溶けやすいため、茹でることである程度除去できます。 ほうれん草や小松菜などを調理する際は、さっと茹でてから使うと鉄分の吸収を妨げにくくなります。
5:アルコールを控える
鉄分の吸収を意識する場合は、アルコールの摂取量にも注意が必要です。アルコールには一部で鉄の吸収を助ける作用があるとされていますが、一方で、がんのリスクを高めるなど健康への悪影響も指摘されています。
6:時間をかけてよく噛んで食べる
鉄分をはじめとする栄養素をしっかり体に届けたい場合は「食べ方」にも意識を向けることが大切です。なかでも、よく噛むことは非常に効果的です。
噛むことで食べ物が細かく砕かれ、唾液がしっかり分泌されます。唾液には消化を助ける酵素が含まれており、胃や腸での栄養吸収がスムーズに進みやすくなります。
さらに、ゆっくり噛むことで満腹感が得られやすく、食べ過ぎの防止にもつながります。忙しい日々のなかでも、しっかり噛んで食べる習慣を心がけ、鉄分をムダなく体に届けましょう。
7:身体環境を整える
鉄分は主に腸で吸収されるため、身体の健康状態が吸収率に大きく影響します。身体環境を整えるためには、乳酸菌やビフィズス菌といったプロバイオティクス、オリゴ糖や食物繊維などのプレバイオティクスを一緒に摂ることが効果的です。
8:サプリメントや栄養補助食品で補う
食事だけで十分な鉄分を摂取するのが難しいと感じる場合は、サプリメントや栄養補助食品を取り入れるのもひとつの方法です。
ただし、製品によって吸収率や胃腸への負担が異なるため、自分の体質に合ったものを選ぶことが大切です。また、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、用量は必ず守りましょう。
鉄分の主な役割と働き
機能鉄と貯蔵鉄
鉄分は体内で「機能鉄」と「貯蔵鉄」の2つに分類されます。
機能鉄は、体内の鉄のおよそ70%を占める成分で、赤血球のヘモグロビンや筋肉内のミオグロビン、各種酵素に含まれます。健康的な生命活動に直接関わる働きをしているのが特徴です。
一方、残り約30%を占める貯蔵鉄は、フェリチンやヘモシデリンという形で肝臓や脾臓、骨髄に蓄えられています。体内の鉄が不足すると、ここから鉄が血液中に放出され活用されます。
つまり、鉄分は「今使うための鉄」と「将来の備えとしての鉄」の2段階でバランスよく管理されているのです。
吸収率が違う!ヘム鉄と非ヘム鉄とは
鉄分の種類は「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2つです。
まず、ヘム鉄は肉や魚、レバーなど動物性食品に含まれています。10〜30%ほど体内での吸収率が高く、効率よく摂取できるのが特徴です。
一方、非ヘム鉄は、野菜や豆類、海藻などの植物性食品に含まれています。1〜8%と吸収率は低く、食事の内容によって吸収率が左右されやすくなります。
鉄分補給を効率よく行うためには、食品の種類や組み合わせを意識するとよいでしょう。
スーパーやコンビニで買える!鉄分を多く含む食材
ここでは、動物性・植物性の食品、飲み物に分けて、日常に取り入れやすい鉄分食材を紹介します。
動物性食品
下表のように動物性食品は、吸収率が高い「ヘム鉄」を豊富に含んでいます。
| 食材 | 鉄分含有量(mg/可食部100gあたり) |
| かたくちいわし | 18.0 |
| 豚レバー | 13.0 |
| 鶏レバー | 9.0 |
| ビーフジャーキー | 6.4 |
精肉・鮮魚はスーパーで簡単に手に入ります。また、コンビニでも冷凍食品やお惣菜として使われているため、日々の食事に無理なく取り入れやすいでしょう。
植物性食品
鉄分豊富な植物性食品は、下表のとおりです。
| 食材 | 鉄分含有量(mg/可食部100gあたり) |
| 岩のり | 48.0 |
| 乾燥きくらげ | 35.0 |
| 大豆 | 9.0 |
| 切り干し大根 | 3.1 |
スーパーの野菜・乾物コーナーで購入でき、コンビニでも納豆や冷凍ほうれん草などが手軽に買えます。
1日にどれくらい摂ればいい?鉄分の推奨摂取量
1日の鉄分推奨摂取量は、下表のとおりです。
| 年齢 | 男性 | 女性(月経あり) | 女性(月経なし) |
| 18~29歳 | 7.5mg | 10.5mg | 6.5mg |
| 30~49歳 | 7.5mg | 10.5mg | 6.5mg |
| 50~64歳 | 7.5mg | 11.0mg | 6.5mg |
| 65~74歳 | 7.5mg | ー | 6.0mg |
| 75歳以上 | 7.0mg | ー | 6.0mg |
| 妊婦(付加量) | |||
| 妊娠初期 | ー | ー | +2.5mg |
| 妊娠中期・後期 | ー | ー | +9.5mg |
| 授乳期 | ー | ー | +2.5mg |
人によって必要な鉄分の量は違います。年齢や性別、妊娠の有無に応じて、自分に合った摂取目安を確認しましょう。
月経・汗・食生活……女性に鉄分不足が多い理由
鉄分は、健康的な生命活動に欠かせない栄養素です。しかし、日本人の鉄分摂取量は、男女ともに推奨量を下回っているのが現状です。とくに女性は鉄分不足になりやすく、慢性的な鉄欠乏状態に陥っている人も少なくありません。
ここでは、主な要因を詳しく見ていきましょう。
そもそも鉄は身体に吸収されにくい
鉄は、摂取した量のうち約10%しか腸で吸収されません。
体内には通常3〜4gの鉄が存在しますが、毎日約1mgが自然に失われています。また、1mgの鉄を体に取り込むためには、約10mgの鉄を食べ物から摂る必要があります。
月経のある女性は男性より多くの鉄分が必要
女性が鉄分不足に陥りやすい大きな理由のひとつが「月経」です。
1回の月経で失われる鉄分は0.55mgとされており、補うには、日々の食事から多めに鉄分を摂取する必要があります。しかし、月経で失われた鉄を毎日の食事だけで十分に補えていないケースが少なくありません。
そのため、日常の食事に加えて、鉄を効率よく補えるサプリメントなどを適切に取り入れましょう。
汗からも鉄分は失われる
汗をかくことで、体内の鉄分は少しずつ失われていきます。
具体的には、1Lの汗をかくと、およそ0.3〜0.4mgの鉄が失われるといわれています。普段の生活では気にならない量かもしれませんが、暑い季節に屋外で作業をする方や、日常的に運動でたくさん汗をかく方にとっては、無視できない数値です。
汗を多くかいた日には、いつもより意識して鉄分を補給することが大切です。
過度なダイエットや不規則な食生活も鉄分不足の原因に
極端なダイエットや乱れた食生活は、鉄分不足を引き起こす原因になります。
女性に多いのが、カロリーや糖質を意識しすぎて、鉄を多く含む肉や豆製品を避けてしまうパターンです。また、朝食を抜いたり、食事の時間が不規則だったりすると、必要な鉄分を1日の中で摂ることが難しくなります。
鉄分の過剰摂取の影響
鉄分の過剰摂取は消化器の不調や鉄過剰症を引き起こす
通常の食事から鉄分を過剰に摂ることはまれですが、サプリメントなどを自己判断で長期間摂取しすぎると、胃のむかつきや便秘などの症状を引き起こすことがあります。
鉄分は「多ければ多いほどよい」わけではなく、必要な量を適切に保つことが健康維持のポイントです。
まとめ
鉄分は、健康を支える大切な栄養素です。しかし、多くの人が鉄分不足に気づかないまま日々を過ごしており、健康面に影響が出ることも少なくありません。
まずは、自分に必要な鉄分量を知り、無理なく続けられる方法で取り入れていくことが大切です。食事の工夫やサプリメントの活用など、自分に合った続けやすい方法を見つけましょう。
健康的な暮らしを送りたい方には「サジーワン」がおすすめです。サジーワンは、鉄分をはじめ、ビタミン・アミノ酸・ポリフェノールなどの栄養素が含まれたドリンクです。栄養バランスの取れた食生活のサポートにぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
「サジーワンオーガニック」の詳細はこちらからご覧ください。