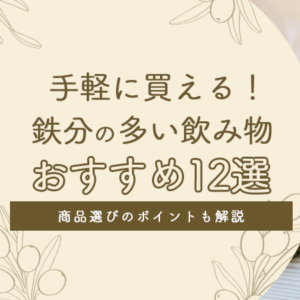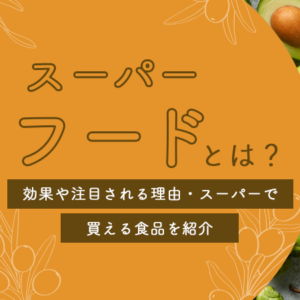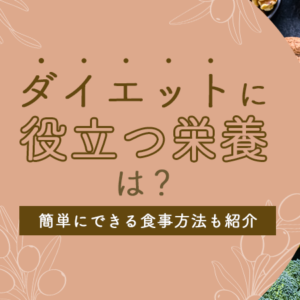
サジーコラム
Column
鉄分が豊富な食べ物リスト!手軽にできる吸収率アップのコツも解説
栄養 2025.02.26

鉄分は、私たちの健康を支えるうえで欠かせない大切な栄養素です。不足すると、疲れやすくなったり、集中力が続かなかったりと、日常生活にさまざまな悩みがあらわれることもあります。
「何を食べれば効率よく鉄分が摂れるのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、鉄分が豊富な食べ物のリストや手軽に吸収率をアップさせるコツを解説します。
鉄分の含有量が多い食べ物丨毎日の食事に取り入れやすい食品一覧

鉄分を不足しないようにするには、日々の食事からしっかり摂ることが重要です。 ここでは、普段の食事に無理なく取り入れやすく、鉄分を豊富に含む食品を一覧で紹介します。
動物性食品
鉄分は一般的に吸収されにくい栄養素ですが、動物性食品に含まれる「ヘム鉄」は体に吸収されやすいのが特徴です。 とくに、以下の表にあるような肉類や魚介類は、鉄分を効率よく摂取できる代表的な食品です。
| 食品名 | 可食部100gあたりの鉄分量 |
| カタクチイワシ(煮干し) | 18.0mg |
| 豚レバー | 13.0mg |
| 鶏レバー | 9.0mg |
| 砂肝 | 9.0mg |
| しじみ | 8.3mg |
| 牛レバー | 4.0mg |
| あさり | 3.8mg |
| コンビーフ | 3.5mg |
| 和牛肉 | 2.8mg |
| はまぐり | 2.1mg |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
とくに、煮干しのカタクチイワシは出汁を取る際に使用できるため、日々の食事でも取り入れやすいでしょう。ほかにも、レバーは近くのスーパーマーケットでも購入できるためおすすめです。
あさりやしじみ、はまぐりといった貝類も鉄分を多く含んでいます。もし、下処理が大変な場合は、すでに調理済みの缶詰になっているものを使うのもひとつの方法です。
植物性食品
植物性食品は、鉄分の吸収率は低いですが、さまざまな食材とあわせやすく、手軽に摂取できます。代表的な食品は以下のとおりです。
| 食品名 | 可食部100gあたりの鉄分量 |
| 岩のり | 48.0mg |
| 乾燥きくらげ | 35.0mg |
| 焼きのり | 11.0mg |
| 大豆 | 9.0mg |
| 凍り豆腐 | 7.5mg |
| パセリ | 7.5mg |
| がんもどき | 3.6mg |
| 切り干し大根 | 3.1mg |
| 葉大根 | 3.1mg |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
とくに、のりはおにぎりに巻いたり味噌汁に入れたりすれば、日常的に鉄分を摂取できます。また、凍り豆腐やがんもどきなどの大豆製品も鉄分が豊富です。しかし、がんもどきは油で揚げているため、食べすぎには注意しましょう。
ほかにも、乾燥きくらげは炒め物や酢の物にも使え、調理しやすいです。さらに、野菜のなかでは、葉の部分にまで鉄分が詰まっている葉大根もおすすめです。
こちらの記事では、鉄分の含有量が多い野菜ランキングを紹介しています。
含有量の多い食材と吸収率アップの方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
飲み物
鉄分は食べ物だけでなく、飲み物からも摂取可能です。なかでも、アサイーやプルーンのジュースは飲みやすく、美容にも効果があるといわれています。
また、飲むヨーグルトや豆乳も、効率よく鉄分補給をサポートしてくれる存在です。ただし、商品によって含まれる栄養素の違いがあるため、味がついているものを摂取する際には飲みすぎないように意識しましょう。
ほかにも、ココアは鉄分摂取において、おすすめの飲み物のひとつです。実際、砂糖や乳製品などが入った調整ココアには100gあたり2.9mg、何も入っていない純ココアには14.0mgの鉄分が含まれています。
出典:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
コンビニで買えるおやつも摂取源!
食事の準備が難しい場合は、鉄分の摂取源として、コンビニで買えるようなおやつを取り入れるのもよいでしょう。たとえば、ドライフルーツやナッツ類などは、手軽につまめるうえに鉄分も含まれており、間食としておすすめです。
主に摂取できるものの鉄分量は、以下の表のとおりです。
| 食品名 | 可食部100gあたりの鉄分量 |
| カシューナッツ | 4.8mg |
| アーモンド | 3.6mg |
| ピスタチオ | 3.0mg |
| ヘーゼルナッツ | 3.0mg |
| 乾燥レーズン | 2.3mg |
| クルミ | 2.7mg |
| マカダミアナッツ | 1.3mg |
| 乾燥プルーン | 1.1mg |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
しかし、これらを一度に大量に摂取するのは難しいため、補助的な役割として考えるようにしましょう。さらに、現代では鉄分入りのウエハースやビスケットなどもあり、小腹が満たせるのもうれしいポイントです。
鉄分はヘム鉄と非ヘム鉄の2種類がある
鉄分には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。効率よく鉄分を摂取するためには、2つの違いを理解することが重要です。以下では、それぞれどのような特徴があるのか解説します。
ヘム鉄
まず、ヘム鉄は主に動物性食品に含まれており、吸収率が非ヘム鉄よりも5〜6倍ほど高いのが特徴です。
出典:ILS株式会社「ヘム鉄|機能性食品」
胃腸の状態や一緒に摂る栄養素に左右されにくいため、効率よく摂取できます。さらに、ヘムオキシゲナーゼというヘム鉄を分解する酵素によって吸収量が調節されるため、鉄分の過剰摂取にもなりにくいです。
非ヘム鉄
非ヘム鉄は、主に植物性食品に含まれる鉄分で、動物性食品に含まれるヘム鉄に比べると吸収率が低いのが特徴です。 しかし、ビタミンCや動物性たんぱく質など、吸収を助ける栄養素と一緒に摂取することで、体内への吸収率を高めることが可能です。
また、私たちが普段の食生活で摂取している鉄分の多くは非ヘム鉄です。そのため、日常的に鉄分をしっかり摂るためには、吸収を助ける食べ合わせを意識することが大切です。
両方の食べ物をバランスよく摂ろう
それぞれによい部分があるヘム鉄と非ヘム鉄ですが、どちらかだけを積極的に摂取すればよいわけではありません。大事なのは、両方の食べ物をバランスよく摂ることです。
吸収率が高いからといって、ヘム鉄の多い食べ物ばかり摂取すると栄養が偏ってしまい、かえって健康に悪影響が出る可能性もあります。そういった事態を防ぐために、さまざまな食べ物の相性を考慮し、健康的な食生活を継続しましょう。
日常生活で鉄分を摂取しやすくする方法
このように、鉄分は日々の食事から摂取することが重要です。ただし、単に鉄分を含む食べ物を摂ればよいわけではありません。大事なのは、無理のない範囲でバランスのとれた食事を続けることです。
以下では、日常生活で鉄分を摂取しやすくする方法を紹介します。
①鉄分の吸収をよくする食べ物を摂る
鉄分の吸収率は、食べ物の組み合わせ次第で大きく変わるため、相性のよい栄養素と一緒に摂ることが大切です。ここでは、鉄分の吸収をよくするために、どのような食べ物を摂ればよいか解説します。
動物性タンパク質
動物性タンパク質は、鉄分の吸収を促進する代表的な栄養素です。鉄分と結びつくことで腸からの吸収を促進し、赤血球のもとにもなります。とくに、魚や赤身肉は鉄分とタンパク質の両方が豊富です。
ビタミンC
非ヘム鉄でも、ビタミンCと組み合わせることで吸収率が高まります。ただし、加熱するとビタミンCは失われやすいため、注意が必要です。
効果的な食べ方として、レモン汁を使用したり、食後に生のいちごやキウイフルーツをそえるとよいでしょう。ほかにも、じゃがいもやピーマンなど、加熱してもビタミンCが壊れにくい食べ物を摂るのもおすすめです。
クエン酸
クエン酸は、鉄分を体内で吸収しやすい形に変える「キレート作用」があります。果物や野菜に多く含まれていますが、なかでも梅干しは鉄分の吸収率が向上する食べ物のひとつです。工夫次第で、料理の味付けや副菜に手軽に取り入れられます。
また、鉄分は美容のコンディションを保つコラーゲンのサポートにも欠かせない栄養素です。
こちらの記事では、コラーゲンについて解説しています。
効果や摂取方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
②鉄分の吸収を悪くする食べ物を控える
どれだけ鉄分を摂取しても、吸収を悪くする食べ物と組み合わせては、効果は期待どおりに発揮されません。効率よく体に取り入れるためにも、以下に挙げる食べ物はできるだけ控えるようにしましょう。
タンニン
タンニンはお茶やコーヒー、ワインに含まれているポリフェノールの一種です。老化の予防になるといわれていますが、鉄分と一緒に摂取すると吸収を妨げてしまいます。
そのため、食事中は水や麦茶を飲むようにしましょう。タンニンが含まれているものを飲む場合は、時間を空けて食後に楽しむのがおすすめです。
リン
リンは保存性をよくするために、多くの加工食品やインスタント食品に利用されています。健康的な歯や骨を保つために欠かせない栄養素ですが、過剰摂取すると鉄分の吸収を悪くするため、注意しましょう。
普段の食生活ではリンが不足することはほとんどありません。気づかないうちに摂取量が多くなりがちなため、摂りすぎには注意が必要です。
フィチン酸
玄米やとうもろこしなどの穀類に含まれるフィチン酸には、抗酸化作用があり、ビタミンB群の一部として健康に役立つ面もあります。
一方で、フィチン酸には鉄分などのミネラルと結合して体外に排出してしまう性質があるため、過剰な摂取には注意が必要です。 鉄分を効率よく吸収したい場合は、フィチン酸を多く含む食品の摂取頻度やタイミングを調整するとよいでしょう。
シュウ酸
鉄分が豊富な野菜というと、ほうれん草を思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、ほうれん草には、鉄分の吸収を阻害するシュウ酸が多く含まれています。そのため、鉄分の吸収率を上げたい場合は、シュウ酸の含有量も意識しましょう。
アルコール
アルコールは体内で分解される際に、鉄の吸収をサポートするビタミンCを消費します。さらに、腸の働きも低下させるため、鉄分の吸収効率が悪くなる可能性があります。
飲酒の習慣がある人は、鉄分不足になりやすいため注意が必要です。 飲酒の頻度や量を見直すことは、鉄分の吸収を助けるだけでなく、全身の健康維持にもつながります。
③鉄分が豊富な一品を加える
毎日の食事に鉄分が豊富な一品を加えるのも、効果的な方法のひとつです。ただし、特別なものを作る必要はなく、いつもの食事に少し工夫をすれば問題ありません。
なかでも、非ヘム鉄を多く含み、常備に適している食べ物は小松菜やひじきです。たとえば、小松菜のおひたしやひじきの煮物をそえるだけで、1日の鉄分摂取量を大きく底上げできます。
一品だけでも意識すれば、無理なく鉄分を摂取できるうえに健康維持にもつながります。
④健康食品やサプリメントで補う
食事だけでは十分な鉄分を摂りきれない場合は、健康食品やサプリメントを活用するのもひとつの方法です。 とくに、妊娠・出産・月経などで鉄分の必要量が増える時期には、サプリメントの利用が効果的です。
不安がある場合は、医師や薬剤師に相談しながら、自分の体調やライフスタイルに合った製品を選ぶようにしましょう。
⑤鉄鍋や鉄フライパンで調理する
調理器具を鉄製のものに替えることで、手軽に鉄分を摂取する方法があります。鉄鍋や鉄フライパンを使うと、加熱中に食材へ鉄分が少しずつ溶け出し、自然と摂取量を増やすことができます。
とくに、トマトや酢など酸味のある食材は鉄が溶けやすく、煮込み料理などに取り入れると効果的です。また、鉄製の調理器具は熱伝導がよく、食材の旨味をしっかり閉じ込めるというメリットもあります。
ただし、鉄製の鍋やフライパンは定期的な手入れが必要なため、扱いが難しいと感じる場合は、鍋に入れて使える鉄球タイプのアイテムを活用するのもおすすめです。
こちらの記事では、鉄分を簡単に摂る方法についてくわしく解説しています。
スーパーやコンビニで買える食品も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
そもそも「鉄分」とはどんな栄養素?
そもそも鉄分とは、人体に必要なミネラルの一種で、身体に欠かせない栄養素です。そんな鉄分は、日々の活力を保つために私たちの体に存在しています。
成人の体内には3~5gの鉄分がある丨貯蔵鉄と機能鉄
そもそも、微量の金属が人体には含まれていますが、そのなかでもとくに多いのが鉄分です。成人の体内にはおよそ3〜5gの鉄分があり、大きく「貯蔵鉄」と「機能鉄」の2種類に分けられます。
貯蔵鉄は、骨髄や肝臓、脾臓などにフェリチンという形で蓄えられており、体内の鉄が不足した際に補う役割をします。貯蔵鉄が十分にある間は不調が現れにくいため、体内で鉄分が足りなくなっていてもだいたいの人が気づきません。
一方、機能鉄は主に赤血球中のヘモグロビンに組み込まれています。体内の鉄分の約70%を占めており、身体に欠かせない役割をしています。
出典:一般社団法人日本臨床専門医会「血清鉄(Fe)、総鉄結合能(TIBC)、フェリチン(Ferritin)の検査について[ラボ NO.403(2012.8.発行)より」
こちらの記事では、鉄分の効果についてくわしく解説しています。
気をつけたい身体のサインも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
鉄分が不足すると様々な影響が出る
鉄分が不足すると体調にさまざまな影響をもたらします。健康のためにはいつも摂っておきたい栄養素です。
とはいえ、鉄分が不足し始めたからといって、すぐに影響が出るわけではありません。最初のうちは貯蔵鉄が使われるため、この時点でわかりやすい変化はほとんど見られません。
しかし、貯蔵鉄が底をつくと「鉄欠乏」が進行し、体に影響が出てきます。
これらの変化はゆっくり進行するため、自分では気づきにくいことが多いです。だからこそ、日頃から体調の変化に敏感になり、鉄分不足を未然に防ぐことが大切です。
1日あたりの鉄分の推奨摂取量
日本人は鉄分が不足しやすい傾向にあるため、不足する特徴に当てはまる場合はとくに注意が必要です。ただし、年齢や性別、ライフステージによって必要な鉄分量は変わります。そのため、1日あたりの鉄分の推奨摂取量を把握することが重要です。
女性の推奨摂取量
まず、女性の鉄分推奨摂取量は、月経の有無によって変わります。女性の鉄分食事摂取基準は以下のとおりです。
女性の鉄分食事摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 月経なし 推定平均必要量 | 月経なし 推奨量 | 月経あり 推定平均必要量 | 月経あり 推奨量 |
| 10~11歳 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 12.5 |
| 12~14歳 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 12.5 |
| 15~17歳 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11.0 |
| 18~29歳 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 30~49歳 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.5 |
| 50~64歳 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.5 |
| 65~74歳 | 5.0 | 6.0 | ー | ー |
| 75歳以上 | 4.5 | 5.5- | ー | ー |
| 妊婦初期 付加量 | +2.0 | +2.5 | ー | ー |
| 妊婦 中後期 付加量 | +7.0 | +8.5 | ー | ー |
| 授乳婦 付加量 | +1.5 | +2.0 | ー | ー |
妊婦さんは必要量が増える
ほかにも、妊婦さんは必要な鉄分の量が増えます。表からもわかるように、妊娠初期は月経なしの場合の推奨量よりも2.5mg、中期から後期にかけては8.5mg増やさなければなりません。また、授乳中も推奨量よりプラス2.0mgの鉄分を摂取することが求められます。
男性の推奨摂取量
男性は月経や妊娠による鉄分の損失がないため、必要な鉄分量は比較的安定しています。 男性の鉄分食事摂取基準は以下のとおりです。
男性の鉄分食事摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 10~11歳 | 6.5 | 9.5 | ー |
| 12~14歳 | 7.5 | 9.0 | ー |
| 15~17歳 | 7.5 | 9.0 | ー |
| 18~29歳 | 5.5 | 7.0 | ー |
| 30~49歳 | 6.0 | 7.5 | ー |
| 50~64歳 | 6.0 | 7.0 | ー |
| 65~74歳 | 5.5 | 7.0 | ー |
| 75歳以上 | 5.5 | 6.5 | ー |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
鉄分が不足しやすい人の例
鉄分は体に必要な栄養素ですが、多くの人が不足しがちな栄養素でもあります。以下では、日本人全体の鉄分摂取量に触れながら、不足しやすい人の例を詳しく解説します。
もともと日本人には鉄分不足の傾向がある
日本人は、もともと鉄分の摂取量が不足しがちであることが、厚生労働省の調査結果からも明らかになっています。下の表は、男女別にみた1日あたりの鉄分摂取量の平均値です。
鉄分摂取量の平均値(1歳以上、男性・年齢階級別:mg/日)
| 年齢 | 7~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
| 鉄 | 6.5 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 8.8 | 8.3 |
鉄分摂取量の平均値(1歳以上、女性・年齢階級別:mg/日)
| 年齢 | 7~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
| 鉄 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 7.5 |
参考:厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」
1:月経のある女性
月経のある女性は、毎月の出血によって一定量の鉄分を失っているため、慢性的に鉄分不足になりやすいです。とくに、出血量が多い人は必要な鉄分の量も増加します。また、月経期には美容のコンディションにも影響が出ることがあります。
こちらの記事では、生理前の肌荒れについて解説しています。
原因や対策も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
2:妊婦・授乳婦
妊娠中や授乳中の女性は、赤ちゃんに栄養を与えるため、通常よりも多くの鉄分が必要です。とくに、妊娠後期は赤ちゃんの成長に合わせて、摂取すべき鉄分量も増えます。
3:成長期の男女
成長期の男女も、身長の伸びや筋肉の発達にともなって鉄分の需要が増すため、不足しやすいです。とくに、女性は成長期に月経が始まることも多く、さらに鉄分が必要になります。
4:高齢者
年齢を重ねると、食事の量が少なくなったり、活動量が減ったりすることで、鉄分が不足しやすくなります。そのため、鉄欠乏になっていても気づきにくいことがあります。
また、持病や服用している薬の影響で、鉄分の吸収が妨げられるケースもあります。自覚しにくい分、定期的な健康診断を受けたり、少しでも体調に変化を感じたら、早めに医師に相談することが大切です。
5:ハードなスポーツをする人
マラソンやサッカーなど、ハードなスポーツをする人は、汗や赤血球の破壊によって鉄分を多く消費します。運動習慣がある人は、日々のトレーニングに加えて、バランスのとれた食事をすることが、パフォーマンス維持にもつながります。
6:食生活が不規則な人
栄養素を気にしない外食ばかりで、食生活が不規則な人も必要な鉄分を十分に摂取することが難しいです。また、過度なダイエットで食事の量を減らしていたり、肉を食べることを避けたりしていると、鉄分が不足していきます。
7:お酒をよく飲む人
お酒をよく飲む人も、鉄分不足には要注意です。アルコールの過剰摂取は、鉄分の吸収を妨げてしまい、健康にも影響を及ぼします。飲酒習慣がある人は、飲む頻度や量を見直すとともに、鉄分を意識した食事を心がけることが重要です。
鉄分は摂りすぎてもいけない丨最悪の場合は鉄過剰症に!?
鉄分は健康維持に欠かせない重要な栄養素ですが「多く摂ればよい」というものではありません。摂りすぎると「鉄過剰症」を引き起こす可能性があり、体内の細胞がダメージを受けたり、臓器に障害が生じる恐れがあります。
ただし、人体は必要ない鉄分は吸収しないため、通常の食事で過剰摂取になることはあまりありません。しかし、レバーを毎日大量に食べたり、用量を超えてサプリメントを服用したりすると、体内に鉄分が蓄積されやすくなります。
鉄分は「不足しないこと」が大切ですが「摂りすぎないこと」も同じくらい重要です。必要に応じて医療機関に相談し、自分に合った適量を守って摂取しましょう。
サジーワンには、鉄分をはじめ200種類以上の栄養素を含む「サジーベリー」が使用されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
まとめ
鉄分は、美容の調子が気になったり、元気が足りなくなるなど、日々の悩みに深く関わる大切な栄養素です。とくに女性や成長期の子ども、スポーツをする人は不足しやすいため、日頃から意識して摂取することが大切です。
毎日の食事にちょっとした工夫を加えるだけでも、鉄分はしっかり補えます。
鉄分を含む栄養補助食品を活用するのもおすすめです。なかでも「サジーワン」は、サジーベリーをふんだんに使用し、鉄分だけでなくビタミン・アミノ酸・ポリフェノールなどの栄養素も含まれています。
ソーダ割りやゼリーにするなどアレンジも楽しめますので、ぜひ毎日の生活に取り入れましょう。