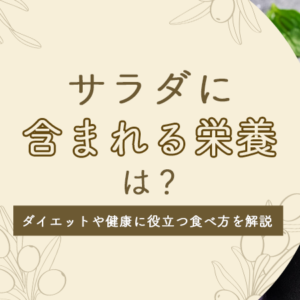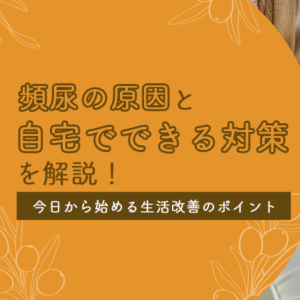サジーコラム
Column
【時間帯別】朝スッキリ起きる方法!今すぐできる改善策
栄養 健康 2025.08.27

朝起きたときに「まだ眠い」「体が重い」と感じることはありませんか。目覚ましを何度もスヌーズにしてしまい、毎朝後悔している方も多いでしょう。
朝スッキリ起きられないと、一日中だるさや集中力の低下につながります。実は朝の目覚めのよさは睡眠時間だけでなく、睡眠の質が大きく関わっています。
この記事では、朝スッキリ起きるための方法を時間帯別に15個紹介します。今日からできる改善策なため、ぜひ参考にしてください。

朝にスッキリ起きられない主な原因
朝スッキリ起きられない背景には、さまざまな原因が隠れています。自分の生活習慣と照らし合わせながら、当てはまるものがないか確認してみましょう。
疲れやストレス
過度のストレスは、朝の目覚めを悪くする大きな原因です。悩みやイライラ、緊張などの心理的ストレスは、脳を活性化させる交感神経を働かせ、寝付けても眠りが浅くなります。
また、疲れすぎている状態も注意が必要です。睡眠中も基礎代謝などでエネルギーを消費するため、あまりに疲れ過ぎていると、眠っても十分に心身が休まらず、翌朝に疲れを持ち越してしまいます。ストレスを抱え込まないようにし、寝る直前はなるべく頭を使わないように意識しましょう。
多忙による不安感
やるべきことが多すぎて整理できていないと、眠る前に不安を感じ、眠れなくなってしまうこともあります。感情が不安定なまま夜を迎えないように、やるべきことや予定を可視化して、頭のなかを整理しておきましょう。
睡眠環境
快適な睡眠を得るためには、寝室環境の整備が重要です。とくに「光・温度・音」の3つの要素が睡眠の質に大きく影響します。
季節に合っていない寝具や、適切でない室温・湿度の環境では、体温調節がうまくいかず睡眠が浅くなります。また、体に合わない枕やマットレスは、自然な寝返りを妨げ、睡眠の質を低下させます。
これらの環境要因を季節や好みに応じて調整することが大切です。
浅い睡眠
睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類があります。入眠直後は脳が深く眠っているノンレム睡眠の状態で、約90分後にレム睡眠に変わります。その後は約90分ごとに繰り返します。
脳や体の疲労を回復する深いノンレム睡眠がとれないと、長時間眠っても脳は十分に休まりません。深い睡眠が取れないと、朝起きた際に熟睡感が得られにくくなります。
アルコール
アルコールには入眠を促す作用がありますが、過度な飲酒は眠りの質を下げます。アルコールの入眠効果は長続きせず、眠りが浅くなって途中で目覚めやすくなります。
また、アルコール分解時に生成されるアセトアルデヒドは覚醒作用を持つため、睡眠の後半で目が覚めやすくなります。少量なら問題ありませんが、寝付くための毎晩の飲酒は避けましょう。
夜遅い食事
食後、胃腸の働きが落ち着くまで約2時間から3時間かかります。就寝前に食べ過ぎると、就寝中も胃腸が働き続けて体が休まらず、脳の血流も低下します。
おなかが満たされた状態で横になると肺に圧力がかかり、睡眠中の酸素量が低下します。また、食事で体温が上がり、寝つきが悪くなります。
睡眠時無呼吸症候群などの病気
日常的にいびきをかいている方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。睡眠時に頻繁に無呼吸になり、脳も体も酸欠状態に陥るため、眠りの質が悪くなります。
十分な時間眠っても疲れがとれない、日中強い眠気に襲われる場合は注意が必要です。また、うつ病や起立性調節障害なども睡眠の質を低下させます。生活習慣の改善で効果がない場合は、専門医への相談を検討してください。
朝スッキリ起きるのに必須の「良質な睡眠」の仕組み
睡眠には、脳が休んでいる「ノンレム睡眠」と、脳が活動している「レム睡眠」があります。眠りにつくとまず深いノンレム睡眠に入り、その後約90分周期で繰り返します。
入眠直後の深いノンレム睡眠時に成長ホルモンが分泌され、体の修復や疲労回復が行われます。また、睡眠中には脳脊髄液の流れが活発になり、脳内の老廃物を排出する「グリンパティックシステム」が働きます。
深いノンレム睡眠をしっかりとることが、朝スッキリ起きるための鍵となります。
時間帯別!朝スッキリ起きる方法
ここからは、朝スッキリ起きるための具体的な方法を時間帯別に紹介します。夜、寝る前、朝の3つの時間帯で実践できる方法をまとめました。今日からできる行動であるため、できることから取り入れてみてください。
夜にできる5つのこと
まずは、夜の過ごし方から見直しましょう。夜の行動が翌朝の目覚めを左右します。
寝る4~8時間前からカフェインの摂取を控える
カフェインは脳を刺激して覚醒状態にし、効果が8時間以上持続することもあります。コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどは、夕方以降の摂取を控えましょう。
理想は就寝の4~8時間前、少なくとも4時間前からはカフェイン摂取を避けることで、寝つきがよくなり、睡眠の質が向上します。夕方以降は、カフェインレスコーヒーやハーブティーを選ぶとよいでしょう。
寝る3時間前までに夕食を済ませる
夕食は就寝の2時間から3時間前までに済ませましょう。寝る直前の食事は胃に負担をかけ、睡眠の質を低下させます。とくに脂肪分の多い肉類や揚げ物は消化に時間がかかるため控えめにしてください。
食事が遅くなる場合は、早めの時間と帰宅後の2回に分ける「分食」が効果的です。夜に空腹を感じたら、消化のよいスープやホットミルクを選びましょう。
寝る2~3時間前に入浴しておく
入浴のタイミングは睡眠の質に大きく影響します。就寝の90分から2時間前までに入浴を終えるのがおすすめです。
38〜40度程度のぬるめのお湯に浸かると、副交感神経が高まり、体温が下がるタイミングで眠気を誘発します。皮膚温度を上げて深部体温を下げることで、良質な睡眠を得られます。
入眠直前に40度以上の熱いお風呂に浸かると、交感神経が優位になるため避けましょう。シャワーでは体の内部まで温まらないため、しっかり浸かることが大切です。
寝る1~2時間前からはPCやスマホを見ない
ブルーライトは体内時計を狂わせ、睡眠サイクルに影響します。スマートフォン、パソコン、テレビから発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンのメラトニン分泌を抑制し、寝つきを悪くします。
就寝の1時間から2時間前にはデジタル機器の使用を控えましょう。「入浴以降はスマートフォンに触れない」「寝室に持ち込まない」といったマイルールも効果的です。やむを得ず使用する場合は、ブルーライトカット機能を活用してください。
飲酒や喫煙を控える
アルコールやタバコは睡眠の質を低下させます。アルコールは入眠を促しますが効果は長続きせず、眠りが浅くなります。ニコチンは交感神経を刺激し、寝つきの悪さや深い眠りの減少につながります。
就寝前の飲酒や喫煙は控えましょう。寝酒の習慣がある方は、ほかのリラックス方法に切り替えることをおすすめします。
寝る前にできる6つのこと
次に、寝る直前にできる工夫を紹介します。寝室環境を整えることで、睡眠の質が格段に向上します。
自分に合った寝具を使う
体型や寝姿勢に合った寝具を選ぶことが重要です。合わない寝具は首や背中に負担をかけ、呼吸がしづらくなったり、寝返りが増えたりして睡眠が浅くなります。
枕は仰向けに寝たときに、首のカーブが自然に保たれる高さを選びましょう。マットレスは体圧が均等に分散され、寝返りがしやすいものが理想的です。
パジャマも重要です。夏は綿や麻のサラリとした素材、冬は起毛など暖かい素材を選び、睡眠をサポートします。
室温を季節に合わせて13~29℃に設定する
寝室の温度を快適に保つことが大切です。研究によると、極端に高い温度や低い温度では睡眠の質が低下します。一般的には、夏は25~28度、冬は18~22度程度が快適とされています。
エアコンや加湿器、除湿器を使い、快適な温度や湿度を保ちましょう。夏にエアコンをつけっぱなしにする場合は、体の冷えを防ぐため、設定温度や風向きを調整し、扇風機も併用するとよいでしょう。
温かいものを飲む
眠る前に温かい飲み物を飲むと、副交感神経が優位になり体を休ませてくれます。深部体温を一時的に上昇させることで、その後の体温低下により自然な眠気を促します。
おすすめは、ホットミルク、白湯、スープ、カモミールティーなどです。牛乳に含まれるトリプトファンは睡眠ホルモンのメラトニンの材料となります。カフェインやアルコール、香辛料は避けましょう。
リラックスできる音楽を聴く
眠る前に穏やかな音楽を聴くとリラックスでき、スムーズに眠りにつけます。激しいリズムの音楽は気持ちが昂るため、ヒーリングミュージックのような歌詞のない穏やかな音楽がおすすめです。
クラシック音楽やジャズのバラード、自然音(波の音、雨の音など)も効果的です。音量は小さめに設定し、タイマー機能で一定時間後に自動で止まるようにしておきましょう。
部屋のカーテンを少し開けておく
朝日を浴びると体内時計がリセットされて目覚めやすくなります。寝室のカーテンを少し開けておくと、自然に太陽の光が部屋に入ります。
遮光カーテン使用時は、自動開閉器具やタイマー式のシーリングライトを活用するとよいでしょう。ただし、街灯などの夜間の光が気になる場合は、遮光カーテンを閉めて暗い環境で眠ることを優先してください。
部屋を暗くして寝る
メラトニンの分泌は周囲の明るさに影響されます。部屋を暗くするとメラトニンの分泌が促進され、自然な眠気を感じやすくなります。
就寝前には照明を落として薄暗い環境を作りましょう。暗闇が苦手な方は間接照明を使用してください。豆電球やナイトライトは目に直接光が入らない位置に設置し、スマートフォンの画面の光にも注意が必要です。
朝にできる4つのこと
最後に、朝の目覚めをよくするための方法を紹介します。起床後の行動が一日を左右し、夜の睡眠の質にもつながります。
まずは朝日を浴びる
起床後すぐに太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされ、約14~16時間後に眠気のスイッチが入ります。また、体を活動モードに切り替えるセロトニンの分泌も促されます。
起きたらカーテンを開け、太陽の光を15秒ほど浴びましょう。睡眠ホルモンのメラトニン分泌がストップし、体も頭もシャキッと目覚めます。
水か白湯を1杯飲む
睡眠中に約200ミリリットルの汗をかくため、起床時の水分補給は必須です。朝一番にコップ1杯の水または白湯を飲むことで、水分バランスが整い、腸の動きも活発になります。
朝の水分補給は体をすっきりと目覚めさせ、体内時計の調整にも役立ちます。冷たい水よりも常温の水や白湯の方が胃腸に負担をかけません。
ストレッチや軽い運動をする
朝のストレッチは、夜間の睡眠で固まった体をほぐし、一日を健やかにスタートさせます。肩こりや背中の凝りを改善し、むくみを緩和する効果があります。
全身の背伸びストレッチが効果的です。仰向けに寝た状態で手足を大きく伸ばし、全身を気持ちよく伸ばしましょう。手首と足首を大きく回すストレッチも、末端の血行を促進します。
耳を揉むマッサージもおすすめです。耳には自律神経を整えるツボが集中しているため、寝起きの体をパッと目覚めさせることができます。
しっかりと朝食を摂る
朝食は体温を上昇させて心身を活動モードに切り替え、体内時計もリセットします。セロトニンの原料となるトリプトファンを含むタンパク質や、エネルギー源となる糖質を意識してとりましょう。
トリプトファンを多く含む食品は、大豆製品(納豆、豆腐)、卵、牛乳、チーズ、ヨーグルト、バナナなどです。朝食にこれらを取り入れることで、日中のセロトニン生成を助け、夜には良質な睡眠につながります。
また、栄養バランスを整えるために、野菜や果物から作られたジュースを取り入れるのもおすすめです。ビタミンやミネラルが豊富なサジージュースなどを朝食時に飲むことで、一日を元気にスタートできるでしょう。
まとめ
朝スッキリ起きるためには、夜の過ごし方、寝る前の習慣、朝の行動という3つの時間帯での工夫が重要です。カフェインや食事のタイミング、入浴の時間、ブルーライトの制限など、今日から実践できる方法ばかりです。
睡眠の質を高めることで、朝の目覚めがよくなるだけでなく、日中のパフォーマンス向上、ストレス緩和、生活習慣病予防など、さまざまな効果が期待できます。まずは自分が取り入れやすい方法から始めてみましょう。