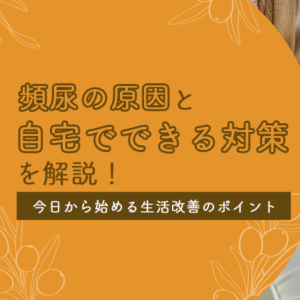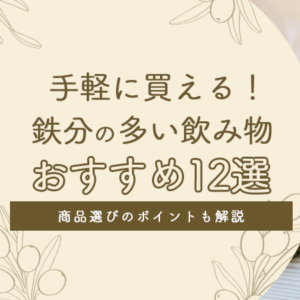
サジーコラム
Column
妊娠中の鉄分不足による症状と赤ちゃんへの影響丨食事でできる予防と対策を解説
栄養 2025.05.01

「妊娠してから、めまいや立ちくらみ、動悸を感じることが増えた」「これって妊娠中の普通の症状なの?それとも鉄分不足…?」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
妊娠中の鉄分不足による貧血は、ママだけでなく赤ちゃんの成長にも影響を与える可能性があります。この記事では、妊娠中の鉄分不足による症状や赤ちゃんへの影響、食事でできる予防と対策について詳しく解説します。

妊婦貧血とは?
妊婦貧血とは、妊娠中に起こる貧血の総称です。貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンが減少し、体内に十分な酸素を運べなくなる状態を指します。
妊娠中は赤ちゃんを育てるために血液量が約1.5倍に増加します。このとき、血液の水分成分である血漿が赤血球の増加より多く増えるため血液が薄まり、相対的にヘモグロビン濃度が低下して貧血状態になりやすいのです。これを「水血症」と呼び、妊娠による生理的な変化です。
妊婦貧血の診断基準は、ヘモグロビン値が11.0g/dL未満(妊娠中期は10.5g/dL未満)、ヘマトクリット値が33%未満とされています。妊婦貧血には主に2種類あります。
鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は、妊婦貧血の大部分を占める最も一般的なタイプです。ヘモグロビンは赤血球に含まれるタンパク質で、酸素を体中に運ぶ重要な役割を担っています。このヘモグロビンを作るために欠かせないのが鉄分です。
妊娠中は赤ちゃんの成長のために母体の鉄分が優先的に赤ちゃんへ送られるため、ママの体内の鉄分が不足しやすくなります。また、つわりで食事がとりづらい時期には栄養バランスが乱れ、さらに鉄分不足を招きやすくなります。
葉酸欠乏性貧血
葉酸欠乏性貧血は、ビタミンB群の一種である葉酸が不足することで起こる貧血です。医学用語では「巨赤芽球性貧血」とも呼ばれます。
葉酸はタンパク質やDNAの合成に必要な栄養素で、赤血球を成熟させる働きも担っています。葉酸が不足すると、赤血球は正常に育つことができず、未熟なまま大きくなって壊れてしまいます。葉酸不足は赤ちゃんの神経管閉鎖障害のリスクを高めることも知られています。
妊娠中の鉄分不足を示す症状
妊娠中の鉄分不足による貧血には、様々な症状が現れます。慢性的な疲労感や倦怠感を感じやすくなります。めまいや立ちくらみ、急に立ち上がったときにクラッとするといった症状は脳への酸素供給が不足しているサインです。動悸や息切れ、頭痛、集中力の低下なども起こりやすくなります。
見た目の変化としては、顔色が悪くなる、唇や爪の色が青白くなるといった症状が現れます。爪がもろくなって割れやすくなったり、スプーン状に変形したりすることもあります。異食症という、氷を無性に食べたくなるといった特徴的な症状が出ることもあります。
上記の症状はあくまで例です。疑わしい場合は自己診断で判断せず、かかりつけの医師や産婦人科医に相談してください。
なぜ妊娠中は鉄分不足になりやすいのか?
妊娠中に鉄分不足になりやすい理由は、主に3つあります。
まず、血液量の増加と血液の希釈です。妊娠中は血液量が約1.5倍に増加しますが、赤血球の増加に追いつかず血液が薄まります。
次に、胎児への鉄分の優先供給があります。赤ちゃんは自分の体内で赤血球を作るために、ママから鉄分を優先的に受け取ります。
最後に、つわりによる食生活の変化も大きな要因です。
妊娠中の鉄分不足が赤ちゃんに与える影響
妊娠中の鉄分不足は、ママ自身の体調だけでなく、赤ちゃんの成長にも影響をおよぼす可能性があります。
最も懸念されるのが、早産や低出生体重児のリスク増加です。貧血によって胎盤への血液供給が不十分になると、赤ちゃんに十分な酸素や栄養が届かず、成長が遅れたり予定日より早く生まれたりするリスクが高まります。
また、ママが貧血の状態で出産すると、生まれてきた赤ちゃん自身も鉄欠乏状態になりやすいという報告もあります。産後については、母乳は血液を原料に作られるため、ママが貧血状態だと十分な母乳が出にくくなる可能性があります。
妊娠中に必要な1日あたりの鉄分摂取量
妊娠中には、通常の約2.5倍もの鉄分が必要になります。
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によると、月経のある成人女性(18〜49歳)の鉄分推奨摂取量は、1日あたり10.5〜11.0mgです。しかし妊娠すると、この基準量に加えて付加量が必要になります。妊娠初期には1日あたり2.5mg、妊娠中期・後期には15.0mgを追加で摂取することが推奨されています。
つまり、妊娠中期・後期の妊婦さんは、1日あたり約25.5〜26.0mgの鉄分が必要です。これは非妊娠時の約2.5倍に相当し、食事だけで満たすのは簡単ではありません。
出典:厚生労働省「鉄の食事摂取基準(mg/日)」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0529-4aq.pdf)
妊娠中の鉄分不足を予防するのにおすすめの食べ物
鉄分には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があり、それぞれ含まれる食品や吸収率が異なります。両方をバランスよく摂取することが大切です。
ヘム鉄を多く含む食べ物
ヘム鉄は主に動物性食品に含まれる鉄分で、体内への吸収率が10〜20%と高いのが特徴です。
豚レバーは50gあたり約6.5mgの鉄分を含み、非常に効率的に鉄分を摂取できます。ただし、レバーにはビタミンAが多く含まれており、妊娠中に過剰摂取すると胎児奇形のリスクがあるという報告があります。レバーを食べる場合は、週1〜2回、1食あたり60g程度を目安にし、頻繁に大量摂取しないよう注意してください。
鶏レバーは50gあたり約4.5mg、牛レバーは50gあたり約2.0mgの鉄分を含みます。レバーが苦手な方には、赤身肉もおすすめです。魚介類では、あさりの水煮が優秀で、100gあたり約30.0mgもの鉄分を含みます。カツオやマグロといった赤身の魚にも鉄分が豊富です。
ただし、生のマグロやカツオ、牡蠣などを食べる際は注意が必要です。妊娠中は生魚介類による食中毒のリスクが高まるため、十分に加熱してから食べるか、生食は控えるようにしましょう。
非ヘム鉄を多く含む食べ物
非ヘム鉄は主に植物性食品に含まれる鉄分で、吸収率は1〜6%とヘム鉄に比べて低めです。しかし、ビタミンCやタンパク質と一緒に摂取することで吸収率を高めることができます。
大豆製品は非ヘム鉄の優秀な供給源です。納豆は50gあたり約1.7mg、油揚げは100gあたり約3.2mg、豆乳は200gあたり約2.4mgの鉄分を含みます。緑黄色野菜も積極的に摂りたい食品です。小松菜は100gあたり約2.8mg、ほうれん草は100gあたり約2.0mgの鉄分を含みます。
ただし、ほうれん草にはシュウ酸という成分が含まれており、鉄分の吸収を阻害する働きがあります。下茹でしてアクを抜いたり、油で炒めたりすることでシュウ酸の影響を減らせます。海藻類もおすすめで、ひじきやわかめには豊富な鉄分が含まれています。
葉酸・ビタミンB12を多く含む食べ物
葉酸欠乏性貧血を予防するためには、葉酸とビタミンB12の摂取も欠かせません。
葉酸が豊富な食品としては、枝豆が100gあたり約260μg、ほうれん草が100gあたり約210μg、アスパラガスが100gあたり約180μgを含みます。ブロッコリーや芽キャベツ、モロヘイヤなどの緑黄色野菜にも多く含まれています。焼き海苔や納豆、レバーにも葉酸が豊富です。
ビタミンB12は主に動物性食品に含まれます。あさりやしじみなどの貝類、レバー、さんまやいわしなどの青魚に多く含まれています。葉酸は水溶性ビタミンで熱に弱いため、調理の際は短時間で茹でる、蒸す、電子レンジを活用するなど、栄養素の損失を防ぐ工夫をしましょう。
鉄分の吸収を助ける栄養・阻害する栄養にも気を付けよう
鉄分を多く含む食品を摂るだけでなく、鉄分の吸収率を高める栄養素を一緒に摂ることで、より効率的に鉄分不足を予防できます。
鉄分の吸収を助ける栄養
鉄分の吸収を助ける栄養は、以下のものが挙げられます。
●ビタミンC
ビタミンCは非ヘム鉄の吸収を大きく促進します。レモンやオレンジなどの柑橘類、パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツなどに豊富に含まれています。ほうれん草のおひたしにレモン汁をかける、小松菜とパプリカを炒めるなど、食べ合わせを工夫しましょう。
●タンパク質
タンパク質もヘモグロビンの材料となり、鉄分の吸収を助けます。肉や魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質を毎食取り入れることで、鉄分の吸収率が高まります。
●クエン酸
クエン酸も鉄分の吸収を促進する栄養素で、レモンや梅干し、酢などに含まれています。
鉄分の吸収を阻害する栄養・成分
一方で、鉄分の吸収を妨げる成分もあるため、注意が必要です。
●タンニン
タンニンは非ヘム鉄の吸収を阻害します。緑茶、紅茶、コーヒーに多く含まれるため、食事中や食後すぐにこれらの飲み物を大量に飲むことは避けましょう。飲む場合は、食事から1時間以上時間を空けることをおすすめします。
●シュウ酸
シュウ酸も鉄分の吸収を妨げる成分です。ほうれん草やたけのこに多く含まれていますが、下茹でしてアク抜きをすることで減らせます。
●フィチン酸
フィチン酸は玄米や豆類に含まれており、鉄分やミネラルと結合して吸収を妨げます。
●リン酸塩
リン酸塩は加工食品に多く含まれています。インスタント食品やスナック菓子、ハムやソーセージなどの加工肉の摂取は控えめにしましょう。
まとめ
妊娠中の鉄分不足は、めまいや立ちくらみ、疲労感といった症状を引き起こすだけでなく、赤ちゃんの発育や出産時のリスクにも影響をおよぼす可能性があります。
妊娠中は通常の約2.5倍もの鉄分が必要になるため、ヘム鉄を含む動物性食品と非ヘム鉄を含む植物性食品をバランスよく摂取することが大切です。
また、ビタミンCやタンパク質など、鉄分の吸収を助ける栄養素を組み合わせることで、より効率的に鉄分不足を予防できます。一方で、タンニンやシュウ酸など鉄分の吸収を阻害する成分にも注意し、食べ合わせや摂取タイミングを工夫しましょう。
定期的な妊婦健診で貧血の有無をチェックし、気になる症状があればすぐに医師に相談することがなにより大切です。信頼できる情報をもとに、安心して妊娠期を過ごしていきましょう。